犬も高齢になるにつれ、内臓機能が低下し腎臓病などの発生が多くなります。
腎臓病の治療は、食事療法なしでは考えられないと言っても過言ではないでしょう。
腎臓の正常な機能をできるだけ長く保つには食事内容はとても重要です。
私の愛犬もシニアなので必ず今後の課題になります。
犬の腎臓病の食事について、情報共有しながら一緒に考えていきたいと思います。
腎臓は毒素を体外に排泄させる重要な臓器
腎臓はおしっこを作る臓器です。
体内の不要な毒素はおしっことなって外に排出されます。
血液中には、代謝の副産物として、必要のない毒素などが溜まっていきます。
腎臓は、それが生体に必要か不要かを振り分けるフィルターの役割をします。
体に必要な物質だけ血液中に残し、毒素はおしっことして排泄します。
腎臓には、このような振り分けフィルターが無数にあるのです。
このフィルターユニットはネフロンという名前で呼ばれます。
腎臓の機能不全
腎臓の機能が壊れてしまう原因はいくつもあります。
- 腎炎などの腎臓病
- 尿路結石
- 感染症
- 毒物による中毒
- 加齢など
腎臓の機能が壊れて、正常に働かなくなった状態が腎不全です。
腎不全には、急性と慢性があります。
急性腎不全は、その名前通り急に発症して急速に進行し、適切な治療をしなければ数日以内に亡くなることもあります。
一方、慢性腎不全は、主に高齢の犬に多く見られ、じわじわと進行します。
高齢犬が元気がないのは、年のせいではなく実は腎臓の機能がかなり悪かったということもあるので注意が必要です。
腎臓病は食事の影響大

腎臓に負担をかけないようにするためには、体内に入る物質に制限をかけなければなりません。
つまり食事制限です。
急性腎不全は入院での集中治療が優先になるので、食事療法が必要になるのは主に慢性腎不全の方です。
腎臓と食事はとても関係が深いのです。
まず口から食事(栄養素)を摂りこむと、体内でエネルギーに変換されます。
栄養素をエネルギーに変換する時、代謝の副産物として出る老廃物は体外に排出されます。
腎臓は、3大栄養素である糖質・脂質・蛋白質のうち、蛋白質から出た老廃物の排泄を担っています。
蛋白質を多く摂取すれば、腎臓はその処理に追われて負担が多くかかることになります。
蛋白質は、エネルギー代謝の過程で「インドキシル硫酸」という老廃物質を産生します。
この老廃物は、尿毒症を起こす主な原因物質になります。
腎機能にできるだけ負担をかけず、腎臓を長持ちさせる為には、蛋白質の摂取量の制限が必要になってきます。
食事制限の3つのポイント
腎臓病の食事は、次の3つがポイントですので、是非覚えておいて下さい。
- 蛋白質
- リン(P)
- ナトリウム
腎臓病の食事で注意すべき、制限すべきなのはこの3つです。
蛋白質制限
蛋白質の代謝で産生される老廃物は、窒素(ちっそ)です。
腎臓は、窒素を最終的に尿素に変えて体外に排出させます。
腎臓の機能が悪いと、窒素がいつまでも血液中に残り蓄積していくのです。
この状態での血液検査をすると、尿素窒素(BUN)という項目が高値になります。
血液中に蓄積していく窒素は、体にとっては毒素です。
蛋白質は生体には欠かせない栄養素ですが、腎臓病がある場合は代謝できる能力が少ないために、蛋白質の量を制限する必要があるのです。
ちなみに蛋白質には動物性と植物性があるのですが、植物性の方が窒素の含有量は少ないです。
腎臓病の犬に与える蛋白源は、動物性よりも植物性の方が負担が少ないということになります。
リンの制限
リンは、検査データなどで「P」と表示されている項目のことです。
リンは、その80%が骨や歯に存在しています。
悪者にされがちなリンですが、DNA、RNA、ATP、細胞膜など構成する大事な成分であり、地味ですがなくてはならない栄養素です。
リンは、体内ではカルシウムとペアになって動きます。
その動きに関わるのが、副甲状腺から出されるパラソルモンというホルモンです。
リンを多く摂りすぎると、パラソルモンはリンの濃度を下げようとします。
リンを下げる為にはペアであるカルシウムも必要になるので、骨や歯にあるカルシウムを溶かして血液中に放出させます。
そして不要なリンは腎臓から排出されるのですが、リンとカルシウムが結合した物質は腎臓に沈着しやすくストルバイト尿路結石の原因になります。
リンを摂りすぎれば、カルシウムと結合させて排泄するように体が働き、その結果、腎臓に沈着してダメージを受けるので、リンの制限が必要になるのです。
ナトリウム制限
ナトリウム=Naclは、塩分のことです。
腎臓は、過剰になったナトリウムも体外に排泄しますが、腎機能が悪いとナトリウムは血液中に残ったままになります。
その結果、血中ナトリウム濃度が高くなるので、血管内の濃度を一定に保つために血管内に水分を引き込んで薄めようとします。
つまり、ナトリウムは血管内の水分を増やすのです。
そうなると血圧は上昇し、心臓に負担がかかります。
血圧が上昇すれば、腎臓への血流も一気に増えるので負担が大きくかかります。
ナトリウム制限は基本であり大変重要です。
腎臓病の療法食に早期に切り替える
腎臓のネフロンは、75%が破壊されるまでは症状も特にありません。
腎臓病は、無症状でステージが軽度である早期に発見できることが重要です。
そしてできるだけ早く食事療法などの対応を開始するのがベターです。
食事療法は、開始が早ければ早いほど良好な経過が望めます。
腎臓の療法食は、蛋白質の含有量20%以下が標準です。
療法食のフードは、はっきり言って美味しくないことが多いようで、なかなか食べてもらえないという飼い主さんの悩みもよく耳にします。
最近は療法食にも多くの種類が出ています。
お試ししてみて、食べてくれそうなものを選んであげましょう。
ナチュラルハーベスト (療法食) キドニア 腎臓ケア
腎臓にトラブルがある犬のための食事療法食です。
日本の獣医師と、米国の獣医師が共同で開発した腎臓の療法食ドライフードです。
フォルツァ10 Forza10 リナールアクティブ(腎臓ケア療法食)
高品質のタンパク質と、タンパク質とリン、ナトリウムの含有量を抑え、カリウム:ナトリウムの比率にもこだわった腎臓病の療法食フードです。
心不全の犬の療法食にも適しています。
【ヒルズ】 犬用 腎臓ケア k/d 缶詰
腎臓病の犬のためにたんぱく質、リン、ナトリウムを調整した特別療法食です。
こちらは缶詰のウェットフードです。
食欲がない、療法食ドライフードではなかなか食いつきがよくない、高齢で食べにくいという時などにお勧めです。
ドクターズケア 犬用 キドニーケア 食事療法食
腎臓病の犬のためにリン、たんぱく質およびナトリウムの含有量が調整された療法食です。
腎臓の健康維持に配慮してオメガ3脂肪酸も配合されています。
アニモンダ インテグラプロテクト ニーレン ウエットフード
パテタイプの腎臓療法食ウェットフードで、トッピングとしてもそのまま食事としても与えることができます。
お肉が好きな愛犬の嗜好性を重視、第一主原料は良質な肉でありながら腎臓に配慮して低タンパクに調節されています。
アニモンダ社は人間用の食肉卸業者ストックマイヤーの子会社、人間用の食材のみを使用しています。
腎臓病の食事を手作りする
腎臓病の食事療法を完全に手作りするのはかなり難しいと思います。
でも市販の療法食はこれまでのものと味がずいぶん変わるせいか、食べてくれない、いったいどうすればよいのか・・・。
腎臓の食事療法のポイントをよく理解し、時々は手作りも加えながら工夫することも必要かもしれません。
1.良質な蛋白質
【候補になる食材】
鶏肉・豚肉・卵・ヨーグルト・カテージチーズ・納豆・豆腐・豆乳・枝豆など
卵はアミノ酸スコアが高く良質な蛋白質です。
さらに植物性の蛋白質を上手に足して、取り入れるようにするのがコツです。


ただし、蛋白質は最低限の量に抑えなければなりません。
《蛋白質の量の目安》
体重×2.2g~体重×3.5gの範囲内
※肉の生食は、腎臓の機能に負担がかかりますので避けてください。
2.エネルギー源
蛋白質を多く使うことができない分、エネルギーを脂質や糖質で補わなければなりません。
最近は、穀物不使用で肉中心のフードが多く、これまではそのようなフードを選んで食べさせていた飼い主さんも多いことでしょう。
でも腎臓の食事療法は、それと真逆の食事に切り替えることになります。
脂質はカロリー源として大事なので、良質の脂を少量足してあげると良いです。
オメガ3などが犬にもお勧めの脂質です。
カロリー不足になると、腎臓の機能だけでなく全身状態の悪化の原因になります。
私が透析室で看護師をしていた時、腎不全で透析を受けていた患者さんの食事には、羊羹やババロアなどの甘いデザートが大抵付いていました。
蛋白質がかなり制限されていましたので、そのような食材を足してカロリー調整されていました。
これは人間の話でそのまま犬には当てはまりませんが、たとえばそういうことという参考の話として書いています。
ただし腎不全の食事と透析食は多少違いがあります。
透析により毒素の排出は週3日ほどは可能になるので、食事制限が透析導入前よりは多少緩くなります。
3.ミネラル分の調整
上記が理想の比率とされます。
でも、これを手作りで測って作ることは現実的に無理と思います。
リンを腸内で吸着させて体外へ排出させるサプリメントなどがあり、病院での処方も可能ですので、獣医師と相談してみて下さい。
人間の透析患者さんもリンの数値が高くなるため、リンを吸着・排出させる炭酸カルシウムが処方されるのが一般的です。
ナトリウム(塩分)は、腎臓が良いか悪いかに関係なく、犬によいことはありません。
味付けなどをしたナトリウムを含む食べ物は、腎臓の食事には論外と言えます。
カリウムは野菜や果物に多いミネラルですが、これも制限が必要になることがあります。
カリウムの数値は、腎臓の機能がどの程度悪いかにもよります。
治療に利尿剤を使っている時には、反対に低カリウムになってしまうこともあります。
カリウムは高すぎても低すぎても重大な影響があるのです。
ナトリウムやカリウムの数値は、血液検査をすればわかります。(Na、Kと表記される項目)
もしカリウムの排泄がうまくいかず数値が上昇するようであれば、制限しなければなりませんが、それはあくまでも医師の判断です。
腎臓病の食事療法は複雑で難しいです。
しかし残された腎臓の機能が少ない場合、犬には継続的な透析治療という手段がないので、食事が命を左右するのです。
飼い主さんも最大限の努力で取り組む覚悟が必要と思います。
まとめ
犬の腎臓病の治療は、食事療法がメインです。
腎臓病の食事は難しく、日常的なことなので、人間でもなかなか守られないことが多いです。
犬の腎臓食の本もありますがそれよりも、医学的根拠に基づいた、人間の腎臓食の本などに一度目を通されてみることをお勧めします。
正しく理解することが大事です。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。














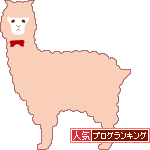
コメント