近年は犬の寿命もずいぶん延びてきました。
その背景には、犬の健康に対する飼い主の関心の高さ・動物医療の発展などがあります。
それでも、老化だけには逆らえません。
長生きになった分、介護の必要な老犬もまた増えています。
老犬の介護の中で問題になりやすいもののひとつに「床ずれ」があります。
床ずれ=褥瘡(じょくそう)は人間の医療介護の現場でも常に大きな課題です。
今回は、看護師の立場からも床ずれの発生と予防についてお伝えできたらと思います。
寝たきりになった老犬には床ずれが発生しやすい
老犬の病気もそれぞれで、治療をしても完治せず慢性的に経過するものも多くあります。
身体機能が衰え、若い時のように動けなくなったとしても、それは覚悟しなければならないでしょう。
病気や怪我をきっかけにして、これまでのADL(日常生活動作)を取り戻せず寝たきりになる老犬もいます。
そして問題になってくるのが床ずれ(褥瘡)の発生です。
床ずれは、同一姿勢で過ごしていることにより同じ部位が長時間の圧迫を受け、その部分の正常な血流が低下または停止されることで起こります。
床ずれは、循環障害による皮膚の損傷です。
血液循環が悪く、組織に栄養分や酸素が届かない状態が一定時間続くと、その組織は阻血性障害を起こし、やがて死滅してしまいますが、この状態が床ずれです。
寝たきりの犬の床ずれは人と同様のものです。
ただ、犬は全身に被毛があるので、それがクッションになるなどして、人よりも皮膚を保護する効果はあると言えます。
その半面、被毛で皮膚の異常が分かりにくく、清潔を保ちにくいことで皮膚の感染症を起こしやすいという欠点もあります。
今は老犬というカテゴリーで書いていますが、床ずれに年齢は関係なく、例えば麻痺があって体を自由に動かせないなどの若い犬もハイリスクです。
床ずれは、一度できてしまうと治りにくく悪化するのも早いため、それが全身状態を左右することもあります。
なので、床ずれは「作らない」ための予防が重要です。
床ずれは骨が出ている部位に好発する
床ずれは、圧迫を受けやすい骨の突出した部位に好発します。
触って骨を感じるようなところと考えるとわかりやすいです。
【床ずれの好発部位】
頬部(ほお)・肩~肩甲骨・前肢や後肢の外側・肘・大腿部・腰など
このような部位が下になって圧迫され続けたり、骨ばった部位同士が重なった状態で長時間経過している場合などに床ずれが発生しやすくなります。
老犬の床ずれリスク
同一部位の長時間圧迫以外に、床ずれができやすくなる他の条件もあります。
老犬は栄養状態も低下していることが多いです。
低栄養だと、低アルブミンにより浮腫が出やすく皮膚の抵抗力が弱いので、皮膚が傷つきやすくなります。
そして全体的に痩せていると、骨も突出やすいです。
皮膚の状態が悪いと、さらに悪い条件がそろってしまいます。
- 皮膚が乾燥している
- 炎症性の皮膚病がある
- 排泄物で常に汚染や湿潤がある
- 浮腫のある皮膚
- 黄疸が出ている皮膚
皮膚が弱っていると外からの刺激に弱く床ずれを起こしやすくなります。
床ずれの予防策その1・皮膚の清潔

寝たきりの老犬には排泄の問題も切り離せないことで、排泄の上手な管理と清潔の保持は、床ずれ予防に重要な課題となります。
オムツ使用の場合も、こまめに取り替えて清潔を保つようにしてください。
オムツの中はただでさえ蒸れやすいです。
排泄物が付いたまま、オムツで蓋をしたような状態では皮膚には最悪の環境です。
汚れて湿った皮膚の状態は、床ずれ発生の温床になります。
被毛のカット
犬は、普段でも、排せつによる汚染を防ぐために肛門周囲やおなかの毛をトリミングで短くカットしたりしますよね。
うちの子はロングコートですが、お尻周りとおなかはいつも短くしています。
寝たきりになるともっと汚れやすくなりますので、できる限り肛門周囲の毛はカットしておいた方が良いです。
せめて毛の長い部分だけでもカットしてあげると汚れ方もずいぶん違いますよ。
尻尾の毛も長くて汚れが付く部分だけでもカットしてあげるとよいと思います。
足裏用の小さいバリカンでも簡単にできますよ。
カットしない場合、尻尾をサポーターなどで包んで保護するのも1つの方法です。
その時は、巻いたままにせず定期的にはずして着け直ししてあげて下さい。
部分浴
全身のシャンプーは無理な場合でも、部分浴で清潔を保つことはできます。
人の医療介護の現場では、寝たきりでも毎日全身を温タオルで拭き、排泄物で汚れる陰部はお湯で洗浄しています。
犬用の「水が不要なシャンプー」も市販されていますので、こういうものを活用するのもよいですね。
拭き取り不要のシャンプータオルはもっと手軽でデイリーに使えます。
冷たいと感じる時は、シャンプータオルをビニール袋に入れてお湯に浸け温めて使うとよいですよ。
お尻を部分浴する時は、ペットシーツを敷き、下の画像のようなお尻洗浄用のボトル(このボトルは人の赤ちゃん用ですが使えそうです)を使用すると洗いやすいと思います。
百均にもこんなボトルがあるかもしれませんね。
洗う時や拭く時は、皮膚を強くこすらないで下さい。
弱っている皮膚をこすると皮膚の表面を容易に傷つけ、これも床ずれの原因になってしまいます。
部分浴をする時は、石鹸やシャンプーの成分を残さないようにすすぎ、水分をタオルでそっと抑えるようにしてきれいに吸い取って下さい。
床ずれ予防策その2・栄養状態の改善
老犬が寝たきりになると、食欲も低下してしまうことが多いでしょう。
栄養状態が悪いと、床ずれができやすくなり、どんなにケアしても治りにくくなってしまいます。
創傷の治癒にはアミノ酸(蛋白質)が欠かせません。
脂肪や筋肉を少しでも増やして栄養状態の改善に努めなければなりません。
流動食
自力で食べることが難しい状態ならば、市販のシリンジを使い、介助で流動食を食べさせてみて下さい。
流動食を食べさせる時は、寝せたままで口に入れるのではなく、できるだけ抱き起して頭を起こす方が自然な飲み込みの形になり、気管への誤嚥の危険も回避できます。
流動食は、フードをふやかしてミキサーにかけても良いです。
ただ、必要な量を食べることができなければ、少量でも高カロリーでバランスのよいものにした方が効率よく栄養を摂取できます。
そこで栄養補助食などを取り入れることをお勧めします。
ミキサー食なら何とか自分で食べられるようなら、もちろん体を支えて介助してあげるのがベターです。
床ずれ予防策その3・摩擦と圧迫の回避
体圧分散マットと体位変換
寝返りなども困難な状態では、血流を停滞させずに床ずれを予防するために2時間おきの体位変換というのが基本となります。
ちなみに人間の病院では、その人の身体条件から床ずれの発生リスクを判定し、ハイリスクスコアの患者さんにはエアーマットというベッドマットを導入します。
エアーマットにもいろんな種類がありますが、一般的に、電動によりマットの内部をエアーが膨張や収縮を自動で繰り返しながら対流し体圧を分散させるといったものです。
犬の介護用品には、電動式ではないですが体圧分散の効果が得られるようなマットも市販されています。
この「耐圧分散」がポイントです。
寝返りが打てない老犬は、寝かせるベッドにはそのようなものを取り入れてあげるとよいと思います。
低反発のマットは体が沈み込み、湿度もこもりやすくなるので個人的にお勧めはしません。
通気性のよい高反発の体圧分散マットは床ずれ予防の効果が期待できます。
そして、体位変換(寝返り)させる際は、必ず一度抱き起して下さい。
肩の下に手を差し入れ、片手は腰を抱えながら抱き起します。
体制を整えたら、老犬の手足を安全に曲げて背中を上にした伏せの姿勢から、それまでと反対の向きにして寝かせます。
犬の体をそのまま仰向けにして、反対側に転がすような寝返りは危険です。
また、ひきずったりする皮膚への摩擦は、床ずれの原因になります。
抱き起こすだけでも血流が改善されます。
起こしたらせっかくの機会ですので、関節の曲げ伸ばしや軽いマッサージなどすると関節の拘縮の予防にもなりますよ。
シーツ類のしわや手足の重なり
寝床に敷いたシーツやタオルなど敷物のしわはできるだけ伸ばして下さい。
しわの寄った部分の圧迫など、小さなことに思えますが、これも床ずれの原因になります。
そして寝かせた姿勢の時にできるだけ手足が直接重ならないようにしましょう。
骨が突出しているかかとや肘の部分は、靴下など履かせて保護してあげるとよいですよ。
上下重なってしまう部分には、その間に小さいクッションを入れて抱かせるなどして、圧迫を避けて下さい。
やわらかいビーズクッションなども結構使いやすいです。
まとめ
床ずれの3大要因は「圧迫や摩擦」「栄養不良」「皮膚の汚染・湿潤」です。
床ずれは一度できてしまうと治療が難しく、悪化すると敗血症などの深刻な病状に陥ることもあります。
床ずれはできてから治療するのではなく予防が重要です。
今は介護用のグッズも多数あり、人用のグッズで応用できるものもあります。
そのようなグッズを上手に活用し、介護する方もされる方もお互いに快適に過ごせるように工夫してみてください。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。











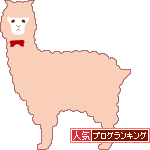
コメント