人と同じように犬にも膵炎という病気があります。
しかも犬の膵炎は、結構多いです。
膵炎は食事と深い関係があるので、食事療法が大変重要です。
そもそも膵臓という臓器の役割が少しわかりにくいと思いますので、今回は膵臓の働きや犬の膵炎、膵炎の食事療法について、皆様と情報共有したいと思います。
膵臓の大きな役割・2種類
膵臓は細長い形の臓器で、胃の後ろにあります。
膵臓には、大きく分類すると2種類の役割があります。
そのうちのひとつは、食事の消化機能です。
膵臓は、消化酵素を分泌します。
膵管という管を通して、膵臓から十二指腸まで消化液を送り出しているのです。
【膵臓から分泌される消化酵素】
- 糖質を分解する:アミラーゼ
- 脂質を分解する:リパーゼ
- 蛋白質を分解する:トリプシン
- 核酸を分解する:ヌクレアーゼ
食事の消化に関わる膵臓の機能は外分泌機能と呼ばれます。
膵臓の役割の90%がこの働きになります。
そして膵臓の2つめの働きは、血糖値をコントロールする役割です。
こちらは内分泌機能と呼ばれます。
膵臓の中には、ランゲルハンス島と呼ばれる細胞群があり、島という字がついていますが膵臓の中の組織の名前です。
その部位から、インスリン(血糖値を下げる)とグルカゴン(血糖値を上げる)という2種類のホルモンを分泌しています。
このホルモンはどちらも糖尿病に関係の深いホルモンです。
インスリンの方は、インスリン注射などがありわりとよく知られている名称ですよね。
これは本来、膵臓から分泌されているのです。
インスリンとグルカゴンの2つのバランスを取ることで、血糖値を一定に保つようにコントロールしているのが膵臓の役割なのです。
簡潔にまとめると・・・
【膵臓の役割】
- 消化酵素の分泌:食べ物の消化に直接的に関わる
- ホルモンの分泌:エネルギー源である糖のバランスを調節する
膵臓は体の奥の方にあるために病気の症状も出にくく、病気の発見もされにくいので、「沈黙の臓器」とも呼ばれています。
急性膵炎と慢性膵炎がある

消化酵素が含まれてる膵液は、とても強力な消化液です。
膵液は本来、十二指腸に流れ込んでから初めて働く仕組みになっています。
ところが、一旦十二指腸に流れた膵液が再び膵臓内に逆流する異常が起こって、膵臓の中で消化酵素が働いてしまうことがあります。
強力な膵液が膵臓の中で働いてしまうと、自分自身の膵臓の細胞も溶かしてしまい、炎症を起こします。
これが膵炎という病気の正体です。
【膵炎の主な症状】
激しい腹痛・嘔吐・下痢・発熱・血便・黄疸など
膵炎の時に見られる消化器症状は、膵炎に限った特徴的なものではなく、他の消化器の病気との区別がつきにくいので要注意です。
膵炎は、嘔吐を繰り返し、容態が悪化するとショック状態に陥り、死亡することもある重大な病気です。
症状が急速に出現して進行するものは急性膵炎です。
何度も急性膵炎を繰り返し、症状が断続的に現れる状態のものは慢性膵炎と呼びます。
食事が膵炎の原因を作る
膵炎の発症には、「脂質の代謝機能に異常のある遺伝子」が関与していると考えられています。
好発犬種は先天的にこの遺伝子を持っている犬が多いようです。
【膵炎の好発犬種】
ミニチュアシュナウザー・トイプードル・コーギーなど
そして犬種だけに限らず、肥満の犬にも膵炎は多く見られます。
つまり食事内容・食習慣が関与してきます。
【膵炎の原因になりやすい食生活】
- 脂肪分を多く摂るような食習慣
- もともと高脂血症がベースにある
たとえ好発犬種でなくても、食事の影響はすべての犬種で起こりうることです。
膵炎を予防するためには普段からの食習慣が重要です。


また、食事以外にも、腫瘍などが膵炎の発症を誘発することがあります。
腫瘍ができて膵臓から十二指腸に繋がる膵管が詰まり、膵液が正常に流れなくなって膵臓内に逆流している状態になると膵炎を発症します。
【膵炎の原因】
- 高脂肪の食事や不規則な食習慣(人間の食事やお菓子など犬には不適切な食べ物を与えるなど)
- 肥満や高脂血症
- 代謝異常を起こす基礎疾患(クッシング症候群、糖尿病、甲状腺機能低下症など)
- 炎症性腸疾患
- 胆のうや胆管の疾患
- 高カルシウム血症
- 外傷・手術・薬物の影響(ステロイド剤、抗けいれん剤、利尿剤など)
- 栄養不良時の急激な食事開始
- 腫瘍等による膵管の閉塞
祈りのポーズと呼ばれる症状
膵炎は一般的に激しい腹痛を伴い、犬に「祈りのポーズ」と呼ばれる独特の姿勢が見られることがあります。
「祈りのポーズ」は伏せでお尻だけを高く上げる姿勢で、遊びに誘う時のプレイバウというポーズにも似ています。
しかしプレイバウとは異なり、「祈りのポーズ」には活気が見られず、尻尾を振るようなこともありません。
《祈りのポーズ》
画像の出典元 https://xn--hhrx3xt0jt8h4kenrxmi6a.com/sick/dog/suien
犬は、痛みに強い生き物です。
しかしこの姿勢は、内臓の圧迫を軽減させて少しでも痛みを和らげようとする姿勢であってかなり深刻な痛みがあることが予測されます。
もちろん痛みがある時に必ずしもすべてこの姿勢になるわけではありません。
うずくまって部屋の隅で痛みに耐えているような場合もあります。
膵炎は早期診断で早期治療を
膵臓は元に戻らない
膵炎は、強い消化酵素で自らの膵臓を自己消化しながら進行します。
炎症がひどくなると、たとえ治療しても膵臓を元の健康な状態に戻すことは難しいです。
重度の膵炎になると、そのダメージは膵臓だけにとどまらなくなります。
膵臓からの膵管が繋がっている十二指腸には、胆のうから胆汁を送る総胆管も繋がっています。
その為、膵炎が重症化すれば炎症は総胆管にまで広がっていくのです。
総胆管が炎症を起こすと、今度は胆汁が停滞し十二指腸に流れなくなります。
もっと進行すると、急性腎不全やDIC(播種性血管内凝固症候群)という重症な全身性の病気へ移行し生命の危険が高くなります。
膵炎の影響は、当然もう一つの膵臓の働きである内分泌機能、インスリンの分泌にも及びます。
膵炎による二次的な糖尿病を発症しインスリン注射が一生必要となることもあります。
進行を少しでも早く食い止める為には、膵炎は軽症のうちの治療が本当に大事です。
膵炎を診断する検査には詳しい血液検査もありますが、結果が出るまでに時間がかかります。
実際の臨床では、症状や発症のエピソードから膵炎という見当を付けて、詳しい検査結果を待つことなく先に治療を開始することも多いようです。
膵炎の治療
膵炎の診断には、炎症反応・アミラーゼ・リパーゼという項目の血液検査を行います。
確定診断は、膵特異的リパーゼ・トリプシン様反応物質という項目の検査で、数値の上昇を確認します。
ただ、膵炎とわかっても治療に対する特効薬はありません。
治療の原則は、膵臓を安静に保つことであり入院治療です。
【膵炎の治療】
- 安静
- 3~4日間の絶飲食
- 点滴による水分と栄養の補給
- 蛋白分解酵素阻害剤などの薬剤投与
痛みや吐き気に対する治療は、鎮痛剤や制吐剤、抗生剤の注射で対症療法を行います。
そして、膵臓の炎症がおさまるのを待つのです。
膵炎の症状が見られなくなれば、少量の水分を飲ませることから始め、少しずつ食事に戻していきます。
治療の経過は大体1週間くらいとされますが、膵炎の重症度でそれも異なります。
もし原因に腫瘍などが見つかれば手術治療も検討になります。
膵炎の食事療法

膵炎は、治療によって症状が消失した後も、生涯に渡っての継続的な食事管理が必要です。
自分の消化酵素で溶けてしまった膵臓の組織は完全には修復できない上に、膵炎はとても再発の多い病気です。
膵炎の再発を予防する為には、低脂肪の食事による徹底した食事管理を続けていかなければなりません。
食事のポイントは低脂肪と消化のしやすさ
【膵炎の犬の食事のポイント】
- 良質な蛋白質を使った低脂肪食
- 消化のしやすさ
脂肪分の多い食事や消化の悪い食事は、消化酵素を多く必要とするので膵臓に負担がかかります。
負担をかけるような食事は避け、膵臓に負担のかからない食事内容に変更しなくてはなりません。
そして、肥満を防止しつつ、必要な栄養素とエネルギーはきちんと得られなければなりません。
【手作り食の時の栄養素の割合目安】
タンパク質3:炭水化物4:脂質3
【消化のよい低脂肪タンパク源の候補】
ささみ・鶏むね肉・鹿肉・馬肉・低脂肪チーズ(無塩犬用)など
他に合併症を持っているかどうかでも食事内容は変わってきます。
また、食事の一回量が多すぎても負担がかかりますので、食事は小分けにして食事回数を増やすのがベターです。
【避けるべき食事】
- 高脂肪の食事
- 脂肪分の多いクッキーやケーキ類などのおやつ
- 食物繊維の多い食事
膵炎の療法食フード
【Daily Style 犬用食事療法食 膵臓サポート 】
獣医師により消化性の高い原材料が厳選され、脂肪を調整して低脂肪を実現した膵臓の療法食です。
【みらいのドッグフード特別療法食 膵臓用】
薬膳をテーマにして作られた「和漢みらいのドッグフード」には、疾患の特性に合わせた療法食が多数あります。
その中で、膵炎やクッシング症候群など、高血糖・高脂血が関わるトラブルや病気のケアを目的とした療法食です。
療法食選びに迷われている飼い主さんは、ぜひ一度ご覧になってみて下さい。
膵炎の食事療法の難しさ
膵炎には食事の習慣が大きく影響する、つまり発症した犬はそれまで高脂肪の食事の習慣があった可能性も高いです。
私達の食事もそうですが、大抵、高脂肪=美味しい食べ物ですよね。
膵炎の犬も、これまでは人の食べ物だったりおいしいおやつなどを与えられてきた習慣があるのかもしれません。
言い換えれば、おいしいものを食べ続けてきたグルメな犬であることが多いとも言えます。
それが病気の治療とは言え、それまでと比べるといきなり味気ない低脂肪の食事に変更されるのです。
人でもなかなか食習慣を変えるのは難しいのに、理由も理解できない犬に食事療法がうまくいかないだろうことは大いに予想がつきます。
低脂肪フードだけではどうしても食べないということで、何とか美味しく食べさせようとして、食事を手作りするようになった飼い主さんもいらっしゃいます。
食べ慣れてきた、好きな食事を食べさせることができないのは可哀想かもしれません。
でも、膵炎は再発が多くそれが怖い病気です。
膵炎を繰り返すと、膵臓のダメージはどんどん深刻になります。
再発させないことが何よりも大事なのです。
そのためには、食事療法は避けて通れない、もっとも重要な対策なのです。
アイスクリームやクッキー、脂肪分の多い肉など、どんなに欲しがったとしても一切食べさせないという姿勢を貫いて下さい。
犬の食事の習慣を変えることは、飼い主さんにも大変なことかもしれません。
食事療法の工夫は水分と温度
飼い主さんは、膵炎の食事にお勧めの食材を把握しておくとよいと思います。
少しでも満足感が得られる工夫をし、食事療法を成功させることが膵炎の治療の成功に繋がります。
キャベツ、ブロッコリー、白米、ジャガイモなども消化がよく、使いやすい食材です。
もちろん量や総カロリーの検討も必要です。
このような食材を使って、水分の多いリゾットのような食事形態にすると消化しやすい上に満足感の得られる食事を作ることができるのではないでしょうか?
ドライフードは、水分を足してふやかすと消化しやすくて同じ量でもかさが増します。
また、温かい食事の方が匂いが強いので、食欲をそそるのには向いていますよ。
フードは一定の温度を越えると栄養素が壊れてしまいますので、温める時やトッピングを乗せたりする時には食材の温度に注意して下さい。
あの手この手で食事の中身を工夫しても、どうしても低脂肪食を食べないかもしれません。
食事を食べなければ栄養が不足してしまいますので、最終手段はペースト状にしてシリンジを使った強制給餌が必要になるかもしれません。
それでも、高脂肪の食事は与えないで下さい。
命がかかっていると考えて食事内容は厳守の姿勢で取り組んで下さい。
まとめ
膵炎は、入院治療で改善して退院した後も厳しい食事管理が必要です。
膵炎が治っても、膵臓は元に戻りません。
膵炎を繰り返せば、やがて膵臓の萎縮が起こり、消化酵素が作られない膵外分泌不全という状態に移行することがあります。
これは全身性の病気を併発して衰弱する原因になり深刻です。
普段から食事内容には十分に注意し、初期症状を見逃さないで下さい。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。












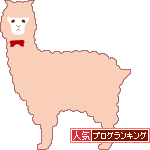
コメント