犬の膝蓋骨脱臼はパテラとも呼ばれます。
特に小型犬に多いので、飼い主さんもよくご存じなのではないでしょうか?
この病気は、症状が軽い時は生活に支障はないですが、ちょっとしたことで悪化しやすく、重度になると歩行困難にもなります。
私の愛犬は、4歳の時に膝蓋骨脱臼の手術をしました。
当時の我が家の体験談も含めて、膝蓋骨脱臼という病気の手術や術後経過のことなどお伝えしたいと思います。
膝蓋骨脱臼(パテラ)は膝のお皿がはずれる病気
膝の関節には、膝のお皿と呼ばれる膝蓋骨(しつがいこつ)という丸い骨があります。
膝蓋骨は、ちょうど膝に蓋をするような形になっていて、前方から衝撃が加えられた時、膝の関節をガードする役割があります。
正常な状態では、膝蓋骨は太ももの骨の滑車溝という溝にきちんとはまって固定されています。
膝を曲げたり伸ばしたりする時には、動きに合わせて上下にスライドし、膝の動きを強化・補助しています。
膝蓋骨の働きのおかげで、太ももの筋肉は安定して十分に筋力を発揮できます。
パテラ(Patella)とは、医学用語で膝蓋骨を指しています。
膝蓋骨脱臼という病気がパテラと通称される理由はここから来ています。
滑車溝からはずれやすい
膝蓋骨脱臼は、膝蓋骨(膝のお皿)が太ももの滑車溝から外れてしまう状態です。
脱臼を起こしやすくなる原因は、
- 滑車溝が浅い
- 膝蓋骨を支えている靭帯が弱い
などが多いです。
膝蓋骨脱臼が起こると、膝の曲げ伸ばしができず、強い痛みがあらわれるようになります。
ところが、また自然と元の位置にはまり、何事もなかったように歩くことも多いのがこの病気です。
脱臼した方の足をあげてケンケンしながら、その足を前後に2,3回振るような動作で自分で整復してしまうことがあります。
はずれたりはまったりしている時は、飼い主さんもまだ気づかないことが多いかもしれません。
遊んでいる時に、急にきゃんと鳴いて足を床に着かなくなり、しばらくすると元の様子に戻っているような時には、膝蓋骨脱臼が疑わしいと思います。
そしてこのように慢性的な脱臼を繰り返しているうちに、膝関節に炎症が起こって関節炎の原因になるので要注意です。
関節炎を起こすと、膝の痛みを常に抱えてしまう状態になって犬のQOLを低下させることになってしまいます。
大型犬にも発症する
膝蓋骨脱臼は、主に小型犬に多い病気です。
だからと言って中型犬や大型犬にないわけではありません。
脱臼は、膝蓋骨が膝の内側方向に外れる内方脱臼がほとんどですが、中型~大型犬では、外側方向に外れる外方脱臼が多く発生します。
これには股関節の病気が深く関係していると言われます。
先天性と後天性がある
膝蓋骨脱臼は、先天性と後天性があります。
上記したように、生まれつき滑車溝が浅い、お皿を支える靭帯が弱いなどの膝関節周辺の形成不全は先天性と言えます。
先天性の原因による膝蓋骨脱臼(形成不全による)
- 大腿骨の滑車溝が浅い発育異常
- 膝蓋骨を支える筋肉や靭帯が不完全な発育異常
- 後ろ足の骨の変形や成長異常
後天性の原因による膝蓋骨脱臼
- 打撲やソファーなどからの落下による外傷
- 足が滑るフローリングでの生活
- 急激な方向転換
- 肥満による膝への負担
後天性は、何らかの強い外力が加わることで発症します。
先天的の素因がある犬に後天性の原因が加わると、より重症化しやすくなります。
診断の流れと重症度を示す基準

膝蓋骨脱臼は、症状と身体検査だけでもほとんど診断はつくようです。
獣医師が触診して膝蓋骨を押しながら、ゆっくり膝を曲げたり伸ばしたりさせると、脱臼があることは大抵確認されます。
私達も自分の膝を触るとわかりますが、膝のお皿の動きはとても柔軟ですよね。
手でゆっくり押してみると、固定されたままで上下左右と可動します。
これは正常な動きで、手を離せばちゃんと元の位置に戻ります。
膝蓋骨脱臼の犬は、お皿を軽く押せば溝から簡単に外れるようです。
さらにその戻り方で重症度が判断されます。
※これはあくまでも獣医師による触診方法ですので、飼い主さんが犬の脱臼を触って確認することはしないようにして下さいね。
診察時には、膝や靭帯の状態、骨の変形などを確認する為にレントゲン検査をします。
手術が必要な状態か、どのような術式が適しているかを検討する材料になります。
膝蓋骨脱臼のグレード分類
膝蓋骨脱臼は、進行の度合いで4段階にグレード分類されます。
グレード1:軽度であり無症状のことがほとんど。膝蓋骨は、普段は滑車溝にはまっていて正常な位置にあり、横方向からの力が加わると脱臼を起こす。
しかし短時間で自然に元の位置に戻る。診察では、膝蓋骨を軽く押すと脱臼が確認できるが、その手を離せば自動的に正常に戻り骨の変形などもない。
グレード2:時々脱臼し、跛行することもある。足を後ろに伸ばして自分で整復出来るため、脱臼した足をピンと何度か後ろに振り上げて伸ばすようなしぐさも見られる。
元に戻ると普通に歩行するが痛みも生じる。その他にも、抱き上げた時に膝が外れることがあるが、日常生活に特別に支障はない。
診察では、膝を曲げると脱臼し、伸ばすと元の位置に戻ることが確認できる。骨の変形が認められることもある。
グレード3:グレード2を放置すると骨の変形や靭帯の損傷を来たし、グレード3に移行するようになる。日常的に脱臼していることが多く、脱臼している足を挙げ跛行することも多い。
跛行がない場合も内股で腰をかがめるように歩き、足は地面に触れる程度でほとんど力をかけることがない。階段の歩行などはできなくなる。膝蓋骨は関節の動きでたまに元の正常な位置に戻る。
診察では、膝を曲げると脱臼し、指で押せば一時的に元に戻せるがすぐに脱臼する状態で、両方に所見が認められることが多い。
グレード4:常に脱臼しているような状態で、歩行異常が顕著になり、膝を曲げてうずくまるような姿勢で歩き活気もなくなる。診察では、指で膝を押しても整復が不可能。骨の変形も重度で、膝を伸ばすことができなくなる。
私の愛犬は、幼犬の時から診察で「両膝とも少し緩くはずれやすい」という指摘を受けていました。
ただ、日常的には目立つ症状はなく、グレード1~2で経過していました。
膝蓋骨脱臼の根治治療は手術

膝蓋骨脱臼は自然に治癒しません。
もちろん足に適切な筋肉をつけることは改善方法のひとつになります。
でも、時期に適した治療や対応を怠ると進行し、骨や周囲の組織まで変形を起こして、将来的に歩行ができなくなります。
将来的に日常的な痛みを抱えることも、犬には大変苦痛でしょう。
根治治療は手術で、グレード3までの間に手術することが推奨されています。
軽度のうちは、環境を調整し、悪化のリスクを回避しながら様子を見ることも可能です。
それでも、グレードが進行し関節や足の変形が重度になってしまってからでは、手術そのものが難しくなってしまうとのことでした。
重度になって手術を行ったとしても完治の可能性も低くなってしまいます。
なので、できるだけ早い時期に手術で根治させることが本当は望ましいです。
手術の適応条件
手術治療が適切な時期かどうかを判断する為の条件もあります。
次の条件に当てはまる場合は、手術の適応になります。
- 生後半年以内の幼犬の膝蓋骨脱臼:成長期に骨が変形し歩行困難になると予想されるため早期手術が推奨
- 生後7カ月以上の犬のグレード2で症状を伴う場合:成犬で症状のないグレード2は経過観察になることもある
- 生後7ヶ月以上の犬でグレード3以上の場合
- 中型犬~大型犬に多い外方脱臼の場合:外方脱臼は腱断裂を起こしやすく関節炎を発症しやすい・痛みの症状も強いことが多い
グレード4は、手術そのものが難しい上に、手術による回復の見込みが少なく手術のリスクも高いことから、積極的に手術適応とはならないようです。
ただ、メリットデメリットを理解した上での飼い主さんの希望もあるので、ケースバイケースになるようです。
うちは、4歳8ヶ月で、手術当時は片側がグレード3に悪化した状態でしたので、3の条件に当てはまりました。
当初は両方手術予定でしたが、結果的に片方だけですみました。
振り返ると、愛犬の体力や麻酔リスクの面からも手術に適した時期だったと思っています。
手術の方法
質関節脱臼の手術は、簡単に言うと、滑車溝という溝を彫って深くし、お皿(膝蓋骨)がしっかりはまるようにしてはずれにくくするのです。
そして、膝周囲の調整をしてお皿の位置も整えます。
滑車溝形成術
膝蓋骨が収まる滑車溝を削って深くする手術で、これがメインと言ってもよいと思います。
ただ膝蓋骨が脱臼して位置もずれていると、溝を深くするだけでは固定できません。
状態に合わせて他の手術も一緒におこなわれます。
頸骨粗面転位術
膝蓋骨の靭帯が付いている部分を一度切り離して、膝蓋骨を正しい位置に修復し、金属製のピンで固定する手術です。
膝蓋骨の位置を骨と整列させ足をまっすぐにするのです。
すると膝にかかっていた偏った力の負荷が解消され、脱臼しにくくなるということです。
愛犬は、この二つの手術を行いました。
ピン固定をしたので、4ヶ月後にピンを抜く手術も受けました。
これは一般的な術式のようですが、他にも何通りもあって、グレードや年齢、体格などによって変更されるようです。
手術のスケジュール
入院日数は平均で1週間~2週間というところのようです。
退院の目安は、病院によっても多少違うと思います。
全身麻酔での手術は、術前に血液検査や心電図など全身のチェックが必要です。
そのスケジュールも含めて、事前に詳しく説明されると思います。
うちの場合、入院の当日に術前検査がおこなわれました。
手術は翌日で、入院は当初、1週間の予定になっていましたが実際には5日間で退院となりました。
愛犬は、回復が順調であったことと、入院によるストレスが犬の負担になっていて、体力を落としかねないことの方が重要と考えられたからです。
入院のストレスにも個体差があり、環境の変化にあまり動じない犬もいれば不適応を起こす犬もいて、うちはどうしても食事が摂れませんでした。
もちろん、退院後に自宅での術後管理が必要なので、どの程度可能なのかも合わせて主治医と話はします。
私は看護師(人の)であり、指示を守ることも環境整備もできるだろうと判断されたと思います。
手術費用
動物医療は自由診療なので、診療費用は病院によって多少ばらつきがあります。
膝蓋骨脱臼の手術費用は、片足の手術入院費込みで20万~30万くらいが相場ではないかという印象です。
愛犬が手術してからもう数年経過しましたが、昨年、知人の犬が手術した時もそれほど費用は変わらないようでした。
費用は地域によっても違い、病院ごとの料金規定もあるので、前もってしっかり確認されて下さい。
何よりもまず、整形専門の獣医師がいるのか、膝蓋骨脱臼の手術に熟練しているかは絶対に確認しましょう。
犬に基礎疾患などがある場合、それも含めた全身管理を安心して任せられるかは、病院選択の重要な条件だと思います。
術後経過・安静とリハビリ
術直後は、手術をした足に圧迫包帯が巻かれて固定されています。
これはずっと巻いておくものではないので、退院の時にはずされているか、退院後に改めてはずしに行く必要があります。
退院後は再脱臼の防止が最重要です。
愛犬は、自宅で4~6週間の絶対安静、ケージレストの指示でした。
↓ケージレストについては、下の記事が参考になります。
ケージレストや安静期間の指示は、術式・その犬の性格・獣医師の方針などでも多少は違うとは思います。
ただ、術後に安静が保てるかどうかで予後は変わってしまうので、これはとても大事なことです。
私は、創部を保護の為にエリザベスカラーを装着させて厳密にケージレストを守らせていました。
エリザベスカラーについては、できるだけ不快のないように柔らかい布製のものを使用していました。
ケージの外をさらに柵を使ってスペースを作り、ご飯の時だけケージから出し、付きっきりで食べさせました。
ケージから出る時の小さい段差も、クッションや毛布を置いてフラットにしました。
術後は、抜糸や検診の為に何度かの通院が必要です。
うちは10日目で抜糸しました。
4週間目の検診では足の状態が順調に回復していたので、ケージレストが解除になりました。
ただし、行動範囲は一つの室内のみで、家中をウロウロさせることはまだ許可されません。
そして、安静度が拡大しても、段差や衝撃を避けること、走らせるのは禁止など行動制限があり、継続して守らなくてはいけません。
また、手術部位の毛を剃ってあるのですが、肌荒れのような状態を起こしました。
ステロイド軟こうを処方され塗っていましたが、なかなか改善せず、セラミドのジェルを処方されて試したらそれが見事に奏功しました。
術後リハビリテーション
ケージレストが解除になると、自宅でも少しずつリハビリ開始が可能ですが、無理をする必要はありません。
私がおこなっていたのは、手術をした足の裏を優しく触る(マッサージ)、抱き上げて足の裏をテーブルなどにおろし、身体を持ち上げたり降ろしたりして足裏の着地の感覚を取り戻す練習などです。
この時点のリハビリは、まだ体重をかけないように支えておこないます。
整形の手術ができる病院は、水中トレッドミルの施設を大抵持っていると思います。
温水を使いその浮力を利用して、体重の負荷なく歩くリハビリが可能な専門施設なので、リハビリ内容を拡大していく時にも安心しておこなえます。
私も予定を立てて予約していましたが、地道に回復し歩けるようになった為、通うには至りませんでした。
愛犬は両膝関節の手術予定だったのに、片方だけの手術ですんだのは、術後に片足がすっかり良くなりもう片方の負担も減ったからです。
グレードが低いとは言え、両足が不安定な時は後ろ足の負担は大きかったでしょう。
手術した足はしっかりして脚力もあり、安定しています。
脱臼の防止のポイントは環境・体重・筋力アップ

膝蓋骨脱臼は、グレードが低く軽度であれば、トラブルがあった時だけ消炎剤の内服薬を使うなどして経過観察するのが一般的だと思います。
あくまでも対症療法で完治するわけではありませんが、犬は痛みや炎症がなくなれば支障なく日常生活を送れます。
でも、グレードが進行するのは本当にちょっとしたきっかけですので、日々の注意が必要です。
私の愛犬が悪化に至ったのは、ある日、ソファーに昇りそこなったことがきっかけです。
うちはフローリングの対策などには注意していましたが、ソファーはそれほど高さもなく、日常的に自分で昇り降りしており私もうっかりしていました。
うまく昇れずにずり落ちてしまい、直後に片足が着かなかったのです。
夜間だったので慌てて救急に連れて行き、パテラのグレード進行を指摘され、手術の検討をアドバイスされました。
翌日、救急の診療情報を持って主治医を受診し、手術の相談をした次第です。
その時にはもう普通に歩けるように回復してはいましたが、ソファーは即日撤去しました。
膝に負担をかけない対処法
体重
悪化リスクの対策の第一は体重コントロールです。
人間もそうですが、体重が増えすぎてしまうと膝関節への負担が大きくなります。
では体重が軽ければ問題ないのかと言えば、そうではありません。
不自然に痩せて筋肉がなければ、身体を支える膝関節へダイレクトに負担がかかります。
適正な体重で十分な筋肉量があり、膝にもしっかり筋肉をつけることが大事なポイントです。
その為にはバランスよい食事と無理のない適切な運動の継続が必須です。
長時間歩かせることも膝に負担がかかるのでご注意下さい。
ダッシュさせたり過剰な運動もかえって負担になるので避けて下さい。
段差解消と滑り止め
滑る、転落するなど、膝に外力がかかる負担をなくした室内環境が大事です。
改善すべき課題でよく挙げられるのはフローリングです。
人にとっては快適なフローリングも、犬は歩きにくく、踏ん張りながら歩いたり走ったりしていることが多いのです。
滑って転倒などすれば、脱臼だけでなく骨折リスクもあります。
フローリングは、特殊な加工で滑り止めコーティングができるワックスもあります。
↓商品紹介ページに動画があるので、滑る床が犬にどのように負担をかけているのかをぜひご覧になってみて下さい。
また、床に密着させて、ずれたり動いたりしないタイル型カーペットなども便利です。
↓このタイルマットは私も使っていますが、撥水で、汚れた部分だけはずして洗えるので便利ですよ。
ソファーや段差が多い環境や、ジャンプして飛び乗る動作もやめさせなければなりません。
段差に昇らせるのなら、スロープやステップなどを設置して下さい。
↓段差を緩やかにするステップです。
足裏のケアとジャンプ禁止
段差に飛び乗る以外にも、後ろ足でピョンピョンと跳ねる動作も悪化の原因になるので極力避けましょう。
急な方向転換も、横からの外力が急激にかかる動作なのでよくないです。
足裏の毛が伸びていると、室内で滑りやすくなります。
足裏の毛のカットは定期的にしてあげて下さいね。
サプリメント
関節に良い成分のサプリメントも多いですね。
病院ではこのサプリメントをお勧めされることが多いようです。
飼い主の間では人気があり、うちも飲ませています。
以前は「アンチノール」でしたが、「アンチノールプラス」に移行していってるようですね。
まとめ
膝蓋骨脱臼の犬はとても多いです。
軽度のうちは日常生活に十分配慮をして経過観察できますが、我が家のように急に進行して手術適応になるパターンもあります。
手術は全身麻酔などゼロリスクではありませんので、最終的には飼い主さん次第だと思います。
うちの犬はその後、心臓病を発症したので、あの時に手術を受けさせて良かったと思いました。
いずれにしても信頼できる獣医師と納得いくまで話し合うことが大事です。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。











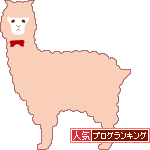
コメント