愛犬が寝ていた場所がおしっこで濡れていたら、飼い主さんにはちょっとショックなことかもしれません。
まさか、もしかしたらお漏らし??
でも待って!叱ったりしないであげてくださいね。
寝ながらお漏らしの原因は病気かもしれません。
今回は、犬のお漏らしの原因と対策について、みなさんと情報を共有したいと思います。
お漏らしは無意識に起こる
お漏らしは「本人の意識とは関係なく排尿が起こる尿失禁のこと」です。
寝ている時に起こる「おねしょ」と同じ現象です。
おねしょのように、いつの間にかおしっこをしてしまう、常に少しずつ漏れているなど、自分で止めることができないおしっこが「お漏らし」です。
~飼い主さんが犬のお漏らしに気づいたのはいつ?~
- 犬が歩いた後の床にいつも水滴が落ちていて、おかしいなと思ったらおしっこだった。
- 犬が寝ていた場所やベッドが何故かいつも濡れていた。実はいつも寝ながらおしっこしていた(おねしょ)。
- いつも足や腹部の毛が湿っている。どうやらおしっこが少しずつ漏れているらしい。
- 陰部が赤くなり炎症を起こしていたので何だろうと思っていた。原因は日常的なお漏らしだった。
まず考えるのは体の病気
お漏らしの症状から考えられる病気はとても多いのです。
泌尿器系の病気の全てにお漏らしの症状はつきものと考えてよいと思います。
たとえば、膀胱炎のような感染症や尿路結石などです。
そして泌尿器と生殖器は臓器が近く密接した位置関係にありますので、子宮蓄膿症などの生殖器の病気もお漏らしの原因になることがあります。
内分泌系(ホルモン)の異常が原因で起こるお漏らしもあります。
例えば、尿崩症という病気の典型的症状「異常な多飲多尿」は、おしっこが多くなるのでお漏らししやすくなります。
そしてこの病気には気づきにくいので注意が必要です。
原因になるメス犬の病気
♠先天的異常
生まれつき泌尿器系の器官(尿道、尿管、膀胱など)の奇形や異常があり、それが原因になっている可能性があります。
子犬の時期から、他に症状もないのにいつもお漏らしだけがある場合はこの可能性が高いです。
特に異所性尿管は、お漏らしの原因になる代表的な奇形です。
異所性尿管は、本来なら腎臓から膀胱に繋がる尿管という器官が、膀胱ではなく尿道や膣に直接繋がっているという奇形です。
そのために腎臓で作られたおしっこを膀胱に送ることができません。
膀胱はおしっこを一旦溜めておく臓器ですが、この奇形があれば膀胱に溜めておくことができず、尿管からそのまま外に漏れ出てしまいます。
異所性尿管のような奇形への対策は、可能な限り手術をして根治治療するのが望ましいのです。
ただ、他に合併症がある場合は手術も難しく、その場合は対症療法しかありません。
♠尿道括約筋機能不全
尿道括約筋機能不全という病気は、先天性と後天性があります。
尿道括約筋は、普段はおしっこが漏れないように閉めておき、おしっこをする時に緩める筋肉です。
この病気は、その筋肉の収縮機能が働かず尿道が緩むので、おしっこが漏れてしまいます。
筋力低下の原因はホルモンバランスで、中型犬や大型犬に多いと言われます。
後天性の場合、避妊手術で卵巣を摘出した後などでホルモンがアンバランスになることと関係が深いとされていました。
しかし術後すでに数年経過していても発症はあり、避妊手術を受けていない犬にもあることから、必ずしも関連性はないようです。
それよりも、肥満や運動不足とその犬の素因が重なることが原因で、特に肥満はハイリスクです。
尿道括約筋機能不全の治療には、女性ホルモンの投与が有効でエストロジェンが使用されます。
括約筋を強化するサプリメントを併用することもあるようです。
原因になるオス犬の病気
♦前立腺肥大
前立腺肥大は、人の高齢男性の病気としてもよく知られていますね。
高齢の男性の排尿困難という症状だと、まずこの病気を考えるほどです。
犬の場合、同じ病気でも排尿より排便困難の症状が出て来ることの方が多いそうです。
この病気は、加齢によりホルモンのバランスが崩れることが原因です。
前立腺肥大に関わるホルモンは、精巣から分泌されるアンドロジェン(雄性ホルモン)とエストロジェン(雌性ホルモン)です。
前立腺というのは、尿道を囲む、精液の成分を作る副生殖器です。
前立腺が肥大すると、その周囲の神経などを圧迫し、お漏らしや血尿などの症状が起こります。
この病気は、4~5歳の未去勢の犬の約半数に見られるとのことです。
未去勢のまま9歳以上になると、そのほとんどに前立腺肥大が認められると言われます。
つまり人間同様に、オス犬には一般的な病気なのです。
予防は去勢手術が有効です。
治療もやはり去勢手術による精巣の摘出です。
手術できない場合は、ホルモン剤(エストロジェン)を投与し雄性ホルモンを抑制して治療することになります。
♦前立腺膿瘍
前立腺膿瘍は、細菌感染により前立腺に膿がたまる病気で膀胱炎から続いて起こることが多いです。
症状は、お漏らしの他に血尿、尿閉(溜まっているのにおしっこが出ない)を起こし、ひどくなると前立腺が破裂してしまいます。
急変して重症になる可能性があるので注意が必要ですね。
抗生物質での治療がメインですが、前立腺の切除が必要になることもあるようです。
オス犬とメス犬に共通の病気
♣腫瘍(良性・悪性)
泌尿器にできた腫瘍が、ちょうど尿管結石のようにおしっこの通り道を塞いでしまったり、神経を圧迫してお漏らしが起こりやすくなります。
♣膀胱炎
膀胱炎は、膀胱内の細菌感染による病気です。
人と同じように血尿・頻尿・排尿時痛などの症状が見られる病気です。
少量ずつのおしっこを何回もするようになるので、トイレに間に合わずお漏らしがおこりやすくなります。
治療は抗生剤の投与ですが、膀胱炎は慢性化すると治りにくく結石を作る原因にもなりやすいので、中途半端な治療にならないようにしなければなりません。
♣結石
尿路結石は、尿路に石ができておしっこの通り道を塞いでしまいます。
おしっこの通り道が詰まってしまうので、激しい痛みがあり、おしっこが出しにくくお漏らしの原因になります。
♣神経障害
神経障害は、事故などによる脊髄損傷や脊髄腫瘍が原因となります。
脊髄には排泄を司る神経があり、そこが傷ついたり切れてしまうと正常な排泄ができません。
神経障害は、自分では排泄コントロールもできません。
治療は原因ごとに違ってきます。
損傷してしまった神経は、現在の医療では簡単に再生させることはできません。
再生医療の発展により、将来的にはそれも治療の1つになる可能性はありますが、今の医療では元に戻すのは困難です。
なので飼い主さん側でおしっこのコントロールをしてやる必要があります。
おしっこを体外に導き出すチューブの挿入なども必要になるかもしれません。
お漏らしの原因はストレスかも?

お漏らしは、明らかに体の病気が原因のものがありますが、そうではないものもあります。
身体には原因がなく、精神的なストレスが原因のこともあるのです。
何か大きな恐怖に遭遇した時や服従行動の延長線でのお漏らしなどがあります。
普段は身体的に異常がないのに、精神的に負荷(ストレス)がかかった時などにこのようなお漏らしが起こります。
お漏らしの対策

観察と記録をする
犬のお漏らしに気づいたら、よく観察しそれに関する情報を記録しておくことをお勧めします。
このような健康上の記録は、病院を受診した時に経過をスムーズに伝える手段としてとても役に立つし、医師の診断の参考になりますよ。
そして治療後の変化を比較して見る時の基本データになるのでとても大事ですよ。
《観察事項》
- 最初にお漏らしがあった年齢と時期
- 去勢手術や避妊手術の既往
- 飲水量とおしっこの量・性状(色やにおいなど)
- お漏らし以外にトイレでも排尿しているか
- お漏らしが起こる状況と頻度
- 現在、病気の治療などで飲ませている薬
- 他に体調の変化はあるか
お漏らしの汚染対策
1.犬の寝床対策
寝ながらお漏らししている時は、とりあえず寝床が濡れない対策を考えましょう。
防水シーツやトイレシートなどをベッド・ベッド周囲に敷きます。
シートで吸水できるようにして、ベッドへの染み込みをできるだけ避けましょう。
ただ防水シーツの上に直接寝せるのは寝心地が悪くて可哀想です。
寝心地が悪いとそこで寝なくなるでしょうから工夫してあげて下さい。
ベッドに防水シーツを敷きその上から洗濯しやすい肌触りの良いシーツを重ねると気持ちよいですよね。
人が宿泊する高級ホテルでも、マットレスの汚染を防ぐ対策に防水シーツが敷いてあります。
あの寝心地なら十分ですよね。
防水シーツは、人間用のおねしょパッドや介護用品が結構使えます。
犬用より種類が多いし、入手しやすいのではないでしょうか。
コストも考えて、惜しげなく使えるものを選ぶと良いですよ。
2.犬の就寝前に膀胱を空にする対策
犬を寝せる前に必ずおしっこをさせてあげましょう。
子供を寝かせる前にトイレに行かせるのと同じですね。
トイレの為だけに短時間の夜の散歩を増やすとか、室内トイレに誘導する習慣をつけるとよいですよ。
「トイレは外派」の犬も多いですが、災害や飼い主さんの病気など様々な状況変化を考えると、外でも室内でも融通が利くようにしておいた方がお互いに楽ですよ。


3.必要に応じておむつで対策
お漏らし対策は、最終的におむつという選択もあります。
お漏らしがあるとそれだけで皮膚も汚れやすく、蒸れて皮膚炎などの二次的な病気の原因にもなりやすいです。
おむつの使用は、お漏らしによる周辺の汚染対策になりますが、皮膚の汚染は避けられません。
それに、おむつをすることでおしっこの観察がしにくいということも理解しておいて下さい。
おむつ使用時は、皮膚を清潔に保ち、決して長時間付けておくことのないようにして下さいね。
おむつ交換時は、温タオルで拭いたり部分浴をするなどし、きちんと乾燥させて皮膚トラブルの予防対策をしてあげて下さい。
そして、おむつは想像以上に暑いのです。
それを考慮した上での気温の調整をしてあげて下さい。



4.ストレスが原因の時の精神的なサポート
お漏らしの原因がストレスと考えられる場合、ストレスの軽減や精神を安定させるなどの対策が必要です。
犬への接し方についても改善点があるはずです。
原因を探って解決に導いてあげて下さい。
お漏らし対策に使えるシーツ
【防水シーツ ドッグケアパッド 速乾性】
おうち時間 在宅 ドッグケア パッド Mサイズ 犬用介護 清潔 速乾性 ドッグケア防水マットレスM
こちらの防水シーツはサイズ展開が3Lまであります。
クッション性に優れ、肌ざわりの良いシーツでおねしょ対策にぴったりですよ。
速乾性もあるのでムレを防ぐことができ、洗濯しやすくて清潔が保てます。
【 防水シーツ《大判サイズ/フラットタイプ》】
[送料無料] 3枚セット 防水シーツ【大判サイズ/フラットタイプ】
こちらは人間の赤ちゃん用のおねしょシーツです。
サイズ展開が豊富で、犬のお漏らし対策に十分に活用できます。
肌触りもよさそうですし、コストパフォーマンスにもすぐれています。
人気商品のようですよ。
まとめ
お漏らしの原因には何かの病気があることも多いのです。
膀胱炎などは犬に多い病気の一つで、早期対策すれば治療もそれほど難しくならないはずです。
こじらせてしまうと、尿毒症などに発展することもあるので早く見つけてあげて下さいね。
お漏らしは、皮膚の汚染・別の感染症の原因にもなるし、犬も不快な状態になってしまいます。
快適に過ごせるように清潔にケアしてあげて下さい。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。










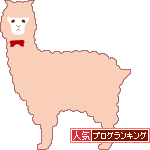
コメント