近年は人も高齢化が進み、85歳以上の4人に1人が認知症と言われる時代になりました。
動物医療の発展によって犬も長寿が増え、介護の問題が取り上げられるようになっています。
その中には人と同様、認知症への対応も含まれています。
今回は、犬の認知症の症状には何があり、診断がどのように行われるか解説したいと思います。
認知症は多様な症状を示す「症候群」である

犬の認知症は人の認知症と同様のものと考えられています。
ここでは、人の認知症を参考にして説明していきたいと思います。
認知症は、認知症という単純な一つの病気ではありません。
認知症の原因は多数あり、それらの原因によって多種多様な症状を表す、認知症という「症候群」を指しています。
認知症を起こす原因になるもの
認知症の症状を引き起こす原因は、大きく3つに分類することができます。
(1)脳の神経細胞の変性によって起こる変性性認知症
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など
(2)頭蓋内の血流低下や血流変化を原因とする脳血管性認知症
脳出血や脳梗塞後などの脳疾患の後遺症による認知症
(3)それ以外の感染症、頭部外傷、脳腫瘍、水頭症、甲状腺疾患などの病気を原因とする認知症
この三つのうち、人の認知症は、(1)の脳神経細胞の減少や変性、委縮によって起こるアルツハイマー型認知症がもっとも患者数が多く、現在、その解明と治療薬の開発が急速に進められています。
アルツハイマー型認知症には、アミロイドβという異常タンパクが深く関係しています。
アミロイドβは凝集して、脳に老人斑(いわゆるシミのようなもの)を沈着させます。
そのことが、脳内の神経系の正常な刺激伝達に障害を起こす原因になるということがわかっています。
また、アルツハイマー型認知症の脳には、脳内の神経伝達に関わるアセチルコリンという物質の著しい減少が認められます。
このような複合的な条件によって、アルツハイマー型認知症は引き起こされます。
ここは専門的な言葉が多いので、少しわかりにくかったかもしれません。
犬の認知症は人のアルツハイマーに似ている
犬の認知症は人のアルツハイマーと類似の脳の病変が認められることが研究でわかっています。
アミロイドβの沈着や、大脳皮質の萎縮、神経細胞の喪失といった脳の変性は、若い犬にはなく老犬に認められるものです。
この脳の変性の進行が、犬の認知症の発症に関係していると考えられています。
原因の全てがそうではないにしても、犬の認知症は人のアルツハイマー型認知症と同様のものが多いと考えることができるのです。
犬の認知症は増えている
最近は、動物医療の発展もめざましく、犬の健康に対する飼い主の意識も向上してきました。
飼育環境は昔と比較して改善され、犬の病気に対する治療の水準も高まって来ました。
それによって、病気の予防が可能になり、病気になっても治癒できる、あるいは、病気と共存しながらも寿命を全うできる犬も増えています。
一昔前に比較すると、長寿で高齢の犬が増えている現在、高齢であるがゆえに慢性疾患を抱えていることも多く、認知症はその中の一つと言えます。
犬の認知症は、専門用語で「認知障害症候群=Cognitive Dysfunction Syndrome(CDS)」と呼ばれ、この10年ほどに研究が進められていった中で、次のようなことがわかっています。
《犬の認知症の臨床的特徴》
犬においては11-12歳の犬の約28%、15-16歳の犬の約68%が1つ以上の認知低下の兆候を示した報告がある。
よく報告される症状としては、以下に示すものがある。
- 見当識障害(Disorientation)
- 相互反応の変化(Interaction changes)
- 睡眠あるいは行動の変化(Sleep or activity changes)
- 家庭でのしつけを忘れる(Housetraining is forgotten)
情報の出典元 https://confit-fs.atlas.jp/customer/acrf35/pdf/Lc2-5.pdf
このような研究が進められるまで、第一に犬の平均寿命は今ほど長くなく、長生きして高齢になった犬に認知症の症状が出現したとしても、それは年齢のせいで仕方ないものであって特に病気の症状という認識はされていませんでした。
つまり、おそらく認知症になっていた犬の症状も、病気ではなく老化による自然なものと捉えられていたのです。
現在になって、犬の認知症が増えている理由は、高齢の犬が増えたことと専門的に認識されるようになったことが理由であると考えられます。
認知症の症状
認知症の症状は、次のように分類されます。
- 見当識障害(Disorientation)
- 相互作用の変化(Interaction)
- 覚醒/睡眠周期の変化(Sleep-wake cycle)
- 不適切な排泄(House soiling)
- 活動性の変化(Activity)
それぞれの頭文字を取って、この分類をDISHA(ディーシャ)と呼び、認知症の症状を確認し診断する時にも、これに基づいたチェックリストが用いられます。
1.見当識障害
見当識障害とは、自分が置かれている状況や今いる場所などがわからなくなる症状です。
人で説明すると、今の年月日や時間、今の季節、自分が誰と話しているかがわからない、途中で間違えるというような症状であらわれたりします。
犬であれば、
- いつもの散歩で慣れているはずなのに帰る方向がわからない
- 家の中や近所なのに迷子になる、混乱したまま家の中を歩き回る
- 壁に向かってただボーっとしている
- 狭い所に入り込んで後退ができない
- 食事する場所にたどり着けない
というような症状が見られます。
2.相互作用の変化
飼い主さんを始めとした、人や他の犬や動物との関わり方がこれまでと変化する症状です。
今までは愛嬌があった犬なのに、
- 抱っこされても撫でられても無反応
- 遊ぶことに全く興味を示さないという症状
- 人や同居動物へのこれまでになかったような攻撃性
という症状が表れやすくなります。
それまでのようにしっぽをふって飼い主さんを迎えるようなこともしなくなり、呼びかけや指示に対しても反応が鈍いという症状も見られます。
または、反対に、過剰に甘えて飼い主さんにつきまとうなどの症状が表れることもあります。
3.覚醒/睡眠周期の変化
睡眠の変化では、昼夜逆転の症状が典型的です。
昼間に寝ていることが多くなり、反対に、夜間は落ち着きがなくなって徘徊や夜鳴き、遠吠えなどの症状が表れるようになります。
過眠(一日中寝ている)と不眠(全く寝ない)のサイクルを繰り返す症状もあります。
【参考記事】
4.不適切な排泄
これまできちんとできていたはずのトイレでの排泄ができなくなり粗相するようになります。
あるいは、前触れなく突然お漏らしをするなどの症状も見られることがあります。
排泄の失敗という症状は、認知症だけでなく、他にも様々な原因があり、身体的な病気の可能性もありますので、見極めが大事です。
【参考記事】
5.活動性の変化
本来、犬が持っているはずの探索欲求が薄れるという症状が表れます。
においを嗅ぐことや音や物への反応が見られないようになってきます。
他にも、
- 食欲が低下するあるいは極端に増加する
- 食べ物や水を探し当てられない
- 同じ場所を舐め続ける
- 一方向に歩き続けて円を描くように旋回する
- ぼんやりして集中力がない
- 壁を見つめる
- 何もない時に吠え続ける
- 鳴き続ける
- 目的なくうろうろと徘徊する
など、様々な症状により活動性が変化してきます。
《徘徊・旋回》
目的もなくうろうろと徘徊する症状は、認知症の特徴的な症状です。
犬が徘徊を始めたら、飼い主さんも必ず異変に気付くという行動ではないかと思います。
認知症では、後ずさって方向転換するという動きができなくなる特徴があります。
徘徊していて、どこかに入り込んでしまい前に進めなくなると、そこから折り返して戻ってくることができず、頭を壁に押し付けた状態のままでそこから動けなくなったりするので、家の中でも目が離せなくなります。
また、誤って犬が外に出てしまうと、帰巣本能も薄れてしまっているために、迷子になりやすく、事故に遭遇するリスクもかなり高くなります。
認知症の徘徊は、進行方向が一定であるため、やがてぐるぐると旋回する症状として見られることも多くなります。
しつけや言い聞かせて修正できるものではなく、旋回や徘徊の症状を止めることは難しいので、あえて安全に徘徊や旋回できる環境を作って対応することが良策になるかと思います。
犬の認知症は、このような症状が最初は1~2個という感じでゆっくり出現し、やがて進行していきます。
多くの症状の進行がゆるやかなものですが、何らかの環境の変化や身体的な病気、ひどく驚くことやショックを受けるような出来事をきっかけに、認知症の症状が急激に悪化することもあります。
また、身体面でも、よく食べていて下痢をしているわけではないのに痩せるなどの症状もあります。
【参考記事】
認知症の診断

人の認知症の診断には「長谷川式認知症スケール」というチェックリストが使用され、診断だけでなく、診断後の治療効果の評価にも使用されます。
長谷川式スケールは9つの質問で構成され合計点数が出せるようになっています。
質問内容は、1:年齢・2:日時の見当識・3:場所の見当識・4:言葉の即時記銘・5:計算・6:数字の逆唱・7:言葉の遅延再生・ 8:物品記銘・9:言語の流暢性といった意味のものです。
このスケールでは、見当識が曖昧でも計算は全く問題ない、い銘力だけが極端に悪いなど、その患者さんによっての症状の偏りもわかります。
犬の認知症も、これと同じように、点数を出して診断する方式のチェックリストがあり、診断基準に使用されることが多いようです。
こちらの画像の診断チェックリストは、1997年に動物エムイーリサーチセンターの獣医師・内野富弥氏によって作成されたものです。
認知症は、このチェックリストにあるように、過去に「痴呆」と呼ばれていましたが、2004年に認知症という呼び方に統一されました。
合計点数はあくまでも診断の目安にすぎないのですが、気になる症状がある場合など、飼い主さんによって自宅でも気軽にチェックしてみることができます。
獣医師は、このような診断スケールの結果を参考にしながら、病歴などの問診、身体検査、神経学的所見、血液検査、尿検査などから総合的に診断を行います。
認知症と同じような症状を引き起こす病気もあるので、それを見逃さない鑑別診断が必要で、診断は消去法になり、これで確実というような認知症に特化した診断方法はありません。
ただ、MRIやCTなどの画像診断では、脳の萎縮や側脳室の拡大などの特徴的な所見が見られることもあります。
画像検査は全身麻酔が必要で、犬にとっても決して負担の少ない検査ではなく、この場合にそれをおこなう意義としては、脳腫瘍などの脳の疾患との鑑別診断です。
認知症に似た症状を示す病気には、脳腫瘍、脳炎、水頭症などの脳神経系や甲状腺機能低下症などの内分泌系疾患、腎疾患などがあります。
または、うつ病などの精神的な病気の初期症状が認知症の初期症状と見分けがつかないこともよくあります。
【参考記事】
治療を受けるためには、正確な診断が必要であり、異変を感じるようなことがあるのならまずは診断を受けさせて下さい。
きちんと診断を受けることで、認知症の進行の程度が把握でき、それは今後の対応方法を考えていくのにも大事なことです。
ただ、比較的新しい分野であり、認識され始めたばかりでもあるため、診断や治療について詳しくない獣医師ももちろんいるようです。
このような病気に理解のある獣医師に診断や治療を委ねることができれば、よりよい対策が立てられるのではないかと思います。
まとめ
認知症は慢性的に進行する病気で、現時点では完治させる方法はありません。
その治療は、薬剤によって症状を緩和し、進行を遅らせながら、環境や食事、飼い主さんの適切な対応などで、犬の生活の質をよりよく保たせるということなのです。
人の認知症は、超高齢化と言われる中で今後も急増することが予測されており、治療薬はそう遠くない未来に発売されるようになると思います。
犬の認知症は人のアルツハイマーと類似点があるので、画期的な治療薬が適用になる日も来るかもしれません。
しかし、認知症は薬だけでなく、対応方法や生活上の工夫も大変重要なのです。
老犬だからと諦めず、病気の症状をきちんと把握して正しい診断に結びつくようにしてあげて下さい。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。






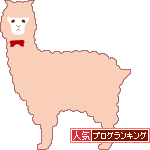
コメント