SNSなどを見ていると、てんかんのある犬は結構多いことがわかります。
私の愛犬もこの病気を持っています。
一度でも発作を見たことのある飼い主さんならわかると思いますが、その姿は決して見慣れることもなく、無力感と不安でいっぱいになります。
てんかん発作には種類があり、とても危険なパターンもあります。
前兆が見られることもあるので、普段から観察のポイントや対処法を把握しておくことをおすすめします。
今回は、犬のてんかんの症状についての情報を共有したいと思います。
犬のてんかんは脳内で起こる異常な電気的興奮

人のてんかんも犬のてんかんも発作のしくみは同様です。
人の看護師の立場で、そのあたりをかみ砕いて説明してみます。
脳内の神経細胞には、正常時な時でもわずかな量の電気が規則正しく流れています。
たまに小さなショートを起こすことがあっても、普通はそれが脳内に広がることにはならずに部分的なトラブルだけで食い止められています。
でも、てんかんという病気は、その働きがうまくいかず、異常なショートがあるとたちまち周囲の神経回路にまで広がります。
これがてんかん発作の正体です。
小さな電気的興奮は、不規則なてんかん発作を繰り返して誘発します。
この発作を症状とした脳の慢性の病気がてんかんと呼ばれる病気です。
てんかんは、人にも多い、ありふれた病気です。
犬も100頭に1頭ほどの割合にあると言われ、珍しい病気というわけではありません。
《てんかん発作の種類》
- 全般発作:突然意識がなくなり痙攣(けいれん)する症状
- 部分発作:意識消失はないが運動機能、視覚、聴覚、自律神経などの異常な症状が現れる
一般にてんかん発作と呼ばれる激しいけいれん発作は、全般発作のことを指しています。
部分発作は、目立たないことが多くて、少し変わった行動とか癖というように感じあることもあると思います。
私の愛犬のてんかん発症時を振り返ってみると、この部分発作だったと思います。
けいれんではないけれど、どこか動作がおかしいと感じることがあったのです。
てんかんは、発作を起こす原因によっても分類があります。
《原因別による分類》
- 症候性てんかん:脳の異常を引き起こす明らかな病気が元々あって、それが引き金となるてんかん発作
- 特発性てんかん:脳自体の異常は見当たらないにも関わらず起こるてんかん発作
てんかんの定義は「反復性発作」です。
一度でも発作が見られれば、それは十分にてんかんが疑わしいと言えるでしょう。
でも、この定義から言えば、単発的な一度だけの発作でまだ診断は付きません。
その発作を繰り返した時(反復)に初めて、てんかんと診断ができます。
特発性てんかんの発作の初発年齢は、6ヶ月~3歳くらいが多いようです。
症候性てんかんの方は、原因になる病気が何であるかによります。
例えば、極端に若い年齢でてんかん発作を起こした場合、脳の奇形など、生まれつきの病気が原因であることも考えられます。
初めて発作を起こした年齢が高齢であれば、脳腫瘍などができている可能性も高いと思われます。
脳腫瘍や脳炎など、脳の病気があるかどうかを調べるためには、CT検査やMRI検査などの画像検査が必要になります。
てんかんは好発犬種もあるため、遺伝的素因が関連する病気とも考えられます。
《好発犬種》
チワワ・ミニチュアダックス・ヨークシャーテリア・パグ・ブルドッグ・ビーグルなど
ただ、多い犬種はあってもその犬種以外にはないというわけではありません。
症候性てんかんの原因になる病気

《てんかん発作を起こす病気》
例えば、ジステンバーなどの重大な感染症にかかったとします。
何とか救命できたとしても、ジステンバーのような神経系の感染症は、脳に後遺症が残る可能性が高いです。
その後遺症がてんかん発作という症状を招く原因にもなります。
このようにして、原因があり引き起こされるてんかん発作が症候性てんかんです。
先天的な奇形では、脳を守るために脳内を満たしている水である脳脊髄液が流れる経路や、脳室の奇形などがあります。
このような奇形では、脳脊髄液が過剰に溜まるので水頭症を起こしやすくなります。
硬い頭蓋骨に覆われた脳の中は容量が限られていて、溜まりすぎた水は脳を圧迫します。
そのせいで脳圧が上昇し、症状としててんかん発作が起こるのです。
水頭症は、外傷などが原因で起こる後天的なものもありますが、先天性や遺伝性のものが多いです。
近年、チワワやトイプードルなどの小型犬は、体格が小さければ小さいほど重宝されて高価に取引される傾向があることをご存知でしょうか?
高く売れる犬を量産させて効率よく利益を上げたい悪徳繁殖業者は、先天疾患や近親交配による遺伝病のリスクなど考えもせず、次々と繁殖させ子犬を産ませます。
こういうものは乱繁殖と呼ばれます。
乱繁殖のせいで頭蓋骨の形成不全などの発生は増え、本来なら閉じていなければならない頭蓋骨の一部に穴が開いていたり、隙間があるなどの奇形も増えます。
そして、水頭症や特発性てんかんなどの病気を抱えて生まれてくる犬が多数いるのです。
全ての先天疾患に当てはまるわけではないですが、安易で乱暴でずさんな交配がこのような遺伝子を持った犬を増やしているのは事実です。
内科的な病気にも、てんかん発作に似たけいれんを起こすものがあります。
それは次のような病気です。
- 低血糖
- 不整脈などの心疾患
- 電解質異常
- ナルコレプシー
- 門脈シャント(肝臓疾患)
- 前庭障害(耳の三半規管)
これらが起こす意識障害や行動障害という症状はてんかん発作と似ているので、鑑別診断が必要です。
てんかんの症状と深刻な発作のパターン
下の図は、人間のてんかん発作が脳内でどのように起こるかを説明したものですが、犬のてんかんも原理は同じなので参考にしてみて下さい。
♦部分発作
部分発作は、脳の一部に異常な電気的興奮が起きている状態です。
その異常が起こった部分の神経がつかさどる体の症状が現れます。
つまり、その脳神経と連動している運動・視覚・聴覚などの異常が症状として起こります。
《部分発作の症状の例》
- 足の片側だけが痙攣する
- 無意味な同じ動作を繰り返す
- 何か噛んでいるような意味のない口の動きを続ける
- 空中に飛ぶ虫(実際には飛んでいない)を追うしぐさをする
- 大量のよだれ
- 瞳孔が開いていて意識がなく呼んでも反応しない
意識障害はある場合とない場合があります。
この状態から、次第に全身に広がって全般発作に発展していくパターンもあります。
♦全般発作
いわゆる、全身のけいれん発作です。
大抵は、それまで特に何の症状もなく過ごしていたということが多いです。
それが突然手足を突っ張らせて横転し、のけぞって全身が痙攣し、手足をばたつかせ口から泡を吹くというような、誰が見てもわかる激しい発作を起こします。
急にバタンと音がして振り返ると犬が倒れて痙攣していた、というように、いきなりの発作の状況を表現する飼い主さんも多いです。
しかし、実は発作の前兆として、
- 何となく落ち着きがなく不安そうにしている
- 嘔吐や震えなど具合が悪そうにしている
などの症状が見られていることもあります。
慣れた飼い主さんになれば、その前兆を見つけ、発作を予測できることもあります。
この時、目は開いていても瞳孔は散大して意識はなく、便失禁や尿失禁などの症状を伴うこともあります。
痙攣しながら転がって周囲の障害物にぶつかることがあるので怪我をする危険もあります。
そして、発作後は、しばらく意識が朦朧として睡眠に移行していくパターンと、ケロッと通常の状態に戻るパターンがあります。
症状がなくなり通常の様子に戻っても、けいれんを起こした後の脳は実はかなり疲労しています。
なので、ぐったりして発熱することもあります。
♦重責発作
てんかんの全般発作の症状のほとんどが2~3分以内で治まるとされています。
ですが、
- 治まりきれず5分以上続く発作
- 発作が終わる前に次の発作がたたみかけるように続けて起こる
以上の2つをてんかん重責発作と呼び、とても危険です。
重責発作になると、体温は急上昇して酸素の消費量が増加するので不整脈や脳の虚血に陥りやすく、脳神経細胞の壊死などが起こって死に至る危険が大きくなるからです。
♦群発発作
5分以内に全般発作が治まったとしても、24時間以内に同様の発作が2回以上起こるものを群発発作と呼びます。
群発発作の回数が多くなるのは危険です。
《重要!》
- 重責発作が30分以上続く
- 群発発作が24時間以内に10回以上起こる
この2つのパターンの発作は脳へのダメージが大きく、死に至る、あるいは救命できても後遺症を残す可能性が高い。
このような発作の症状は緊急治療を要する。
一般的にてんかん発作の症状は、
- 運動後で疲労している時
- 安静時
に起こりやすいと言われます。
また、気圧の変化やその犬にとって発作を誘発しやすい条件(ストレス)などがあります。
- 雷や花火などの大きな音
- チャイム
- 台風
- テレビの映像の光
このようなきっかけで症状が出現することがあるので、誘因になると思われるものはできるだけ避けてあげて下さいね。
私の犬は、一応薬でコントロールできていますが、気圧や気温の変化が影響するようでした。
また、花火や台風などの大きな音がとてもストレスになるようなので、緩和できるように努力しています。
てんかん発作時の対応方法
てんかんの症状を観察し、記録を取っておくことが、てんかんの診断や発作のタイプを見つけるのに役立つので、お勧めします。
てんかんの治療やその犬と暮らす上では、発作のタイプを知りそれをコントロールすることがとても重要なのです。
全般発作のような大きな発作が起こらない限りは、てんかんそのものに気づきにくいかもしれません。
でも、何となく動作や行動がおかしいとひっかかるポイントがあったりします。
私の愛犬のように、変な癖やしぐさが時々あるな・・・と漠然と感じていたことが、後に脳の症状、発作の一種であったと思い当たることもあるかもしれません。
私の犬のしぐさで気になっていたのは、部屋の片隅に行って何かにおびえるような様子や何度も自分の尻尾を振り返る動作を繰り返す、などでした。
それからしばらく経って、本格的な全般発作を起こしたことで、変だと感じていた行動は部分発作だったかもねと獣医師にも言われました。
私は、その些細な「気になる動作」も全部、主治医には相談していました。
解決しなくても、その時点で獣医師に相談しておけば、後で一本の線で繋がることもあるし、診断の参考になります。
大きな発作を起こした時、名前を呼んで意識があるかどうかを確認してみるのは大事なことです。
でも、発作中に大声で呼んで身体をゆすったり触ったりするのは刺激になるのでやめて下さい。
刺激を受けることで発作が激しく誘発されてしまう可能性があるからです。
抑えつけて痙攣を止めようとするのも危ないです。
人のてんかん発作では、舌を噛まないように口の中にタオルや何か物を入れたりは、原則的に禁止されています。
それがかえって窒息の原因になったり、口の中を怪我したりするので危険だからです。
それでも、民間ではガーゼを巻いた箸やスプーンを口に入れて噛ませる処置が正しいといまだに間違った解釈をされていることが多いです。
てんかん発作を起こしている人の救急処置でそのような方法は推奨されません。
【発作時の対応】
- 犬の周辺にある危険な物をよけて安全なスペースを広く確保
- 刺激になる音や光を遮断
- 発作時の屯用の坐薬などがあれば速やかに使用
けいれんしながら動くので、周辺にぶつかったり怪我をすることのないようにして下さい。
テレビなどを消し、部屋の照明も明々としていたら落としてあげて下さい。
発作時の鎮静作用のある坐薬などの指示があれば、入れて下さい。
ただ、発作時は体動がある上に失禁なども見られるので、坐薬を入れるのが難しいかもしれません。
無理だったら抑えつけるなどはせずに少し落ち着くまで見守り、待った方が安全です。
群発発作や重責発作は命に関わる発作です。
連れていける距離や状況であれば、医療機関に連絡を取り搬送して下さい。
この発作は救急対象になる深刻な症状です。
もしもできるなら、発作の様子を動画撮影しておきましょう。
発作の間は、怪我がないように危険なものをよけて、おさまるまで見守るくらいしかなく、手を出せません。
その間に動画が撮れるようなら、スマホなどで短時間でもいいので撮っておくのがよりよいです。
心情的には難しいのですが、もし冷静に撮影できるようであればという話です。
動画を残しておけば、後で獣医師に見せ、診断や治療に役立てもらうことも多いからです。
【てんかん発作の時の観察事項】
- 発作の時間・始まって終わるまでに何分くらいを要したか
- 発作がどの部位からどのように始まり、どのように終わったか
- 発作が起きたのは何をしていた時で、何かきっかけになることがあったか
- 意識の変化はどうだったか
- 発作の前兆や、最近何か変わった行動が見られることがあったか
- 発作以外の症状にはどのようなものがあるか
- 発作後の様子
てんかんの犬の飼い主さんは、てんかん観察ノートのようなものを作っておくと良いですよ。
治療の内容、他の症状、発作の様子などを記録しておくと、後々に発作の前兆や誘発された原因がわかり重宝します。
うちも治療が軌道に乗るまでいろいろなことがありましたので、記録ノートを読み返すと当時のことを思い出します。
てんかんの犬の飼い主さんの不安は、とてもよくわかります。
一緒に、上手に病気と付き合っていきましょう!
まとめ
犬のてんかんの症状は発作という形で表れますが、気づきにくいものから深刻なものまでパターンもいろいろあります。
てんかん発作が起こるたびに脳はダメージを受けます。
そのダメージが次の発作を誘発すると考えられるので、発作をコントロールしてできるだけ予防し、脳を守ることがてんかんの治療です。
病気を受け入れて、適切な治療を受けさせてあげて下さいね。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。









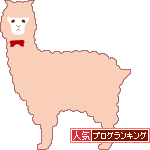
コメント