愛犬のごはんやおやつにキャベツを食べさせる飼い主さんは多いのではないでしょうか?
うちの子も時々食べていますよ。
結構食いつきがよい食べ物ですよね。
ただ、キャベツを犬の食べ物にするには注意点もありますので、是非チェックしておきましょう!
キャベツの栄養素は犬にも良いもの
ビタミンU
キャベツの栄養素で特徴的なもの、それはビタミンUです。
あまり聞かないビタミンかもしれませんが、別名を聞くときっとわかりますよ。
ビタミンUの別名はキャベジンです。
キャベジンと言えば、胃薬の名前で有名ですよね。
それと同じ、キャベジンです。
なんと、キャベジンとは実はキャベツ特有のビタミンのことなのです。
キャベジンには、胃粘膜を保護し粘膜再生を促して炎症や潰瘍を予防する働きがあります。
消化吸収を助け、むかつきなどの消化器症状を予防します。
まさに胃薬そのものですね。
キャベツから発見された薬効成分であるビタミンU(キャベジン)を使って作られたのが、胃薬のキャベジンなのです。
胃薬にそのままの成分の名前がついているということで覚えやすいです。
グルコラファニン
キャベツにはグルコラファニンという成分も含まれています。
これは、アブラナ科の野菜に多い成分で、体に入るとスルフォラファンという成分に変化します。
スルフォラファンは、免疫力をあげてがんの抑制をする働きが期待されているイソチオシアネートという物質の一種です。
いろいろ名前が出て来てわかりにくいですね。
簡単に言うと、キャベツは、抗がん作用が期待される食べ物としても有名なのです。
調理したキャベツの煮汁にも、この成分は溶けていると言われます。
なので煮汁も大事な栄養素になります。
その他
キャベツには、その他、ビタミンC、βカロテン、ビタミンK、カリウム、カルシウムなどの栄養素が含まれています。
葉が紫色をした紫キャベツなどは、あの紫色の部分に抗酸化成分であるポリフェノールが含まれています。
こうして見ると、キャベツは抗酸化作用にすぐれた栄養素を多く含む優秀な野菜と言えます。
その上にキャベツのカロリーは100gで23Kcalと、とても低カロリーでヘルシーです。
犬はキャベツを生で食べられる?
キャベツのビタミンは、加熱したりあまり長い時間水にさらしてしまうと、残念なことに水に溶けて減ってしまいます。
ですので、栄養という点だけで考えると生食が理想的な野菜です。
そして生のキャベツを犬の食べ物にしても大丈夫です。
キャベツは、生の方が歯ごたえがあるので犬の嗜好には合っているかもしれません。
ただ、繊維が多い野菜なので消化のことも考えてあげましょう。
犬の腸がキャベツを消化しやすくするために、繊維を切って小さくしてあげて下さい。
繊維質の食べ物は食べさせる量に注意が必要です。
あまりおなかが丈夫ではない犬や老犬などは、やはり腸に負担がかからないように柔らかく加熱してあげた方が良いです。
加熱したキャベツも独特の風味が出るので、おいしく食べてくれますよ。
そしてアレルギーを起こす可能性は、キャベツも例外ではないので気を付けてあげて下さいね。
キャベツの芯も犬の食べ物にできる?

キャベツの芯は、歯ごたえのある部分なので、この硬さを好む犬もいると思います。
でも、キャベツの芯は実は注意が必要な部分なのです。
キャベツの芯には、硝酸イオンという物質が含まれていて、犬には食べさせない方がいいと言われます。
この硝酸イオンという物質は、体内に取り込まれ、腸内細菌によって亜硝酸という物質に変化します。
この亜硝酸が、中毒症状を起こす可能性を持っています。
そして、がんの発生リスクにもなります。
人間には微量で大したことがないとしても、犬は体が小さいので、その影響は人間以上に大きいということが想定できます。
特に、胃腸の弱い犬や老犬の食べ物には、キャベツの芯は避けた方が安全と言われています。
もちろん、食べられる野菜ですので、キャベツの芯を与えたからと言ってすぐに何かが起こるというわけではないですよ。
でも、リスクがあるなら芯の周辺は避けてあげる方がより安全、と考えてはいかがでしょうか?
注意すべき2つの成分
さらにキャベツの要注意な2つの成分についての話です。
キャベツはアブラナ科の野菜で、同じアブラナ科にブロッコリーや白菜も入ります。
この仲間の野菜は、グルコシノレートという物質を含んでおり、それが体内で分解されゴイトロゲンという物質に変わります。
また覚えにくい成分が出てきてしまいましたが、ゆっくりお読みくださいね。
この物質は、ヨウ素の吸収を阻害します。
ヨウ素とは、甲状腺ホルモンを作るための大事な物質です。
ヨウ素が不足すると、甲状腺ホルモンも不足してしまいます。
甲状腺ホルモンは、生体に不可欠なホルモンなので、体はこの不足を補おうとして、甲状腺を刺激するホルモンを過剰に分泌します。
つまり、甲状腺に対して「甲状腺ホルモンを分泌せよ!」と必死で命令するのです。
この甲状腺への過剰な刺激が、甲状腺腫という腫瘍などの原因になりやすいです。
ただ、健康な犬であれば、かなり大量に食べるなどしない限りは心配しなくても良いでしょう。
でも、犬が甲状腺の病気で治療中だったり、甲状腺に問題がある犬の食べ物としては、やはりキャベツとこの種類の野菜は控える方が安心かもしれません。
もう1つの成分は、キャベツに多く含まれるシュウ酸という物質です。
シュウ酸は、体内に入れば、カルシウムと結合してシュウ酸カルシウムになります。
普通はおしっことして体外に排出されるのですが、量が多くなると、うまく排出しきれないものが蓄積し、やがて尿路結石になります。
このような理由から、キャベツは結石の治療中や結石ができやすい体質の犬の食べ物としては注意すべきです。
シュウ酸を含む野菜は、キャベツ以外にも結構多いので気を付けて下さい。
ちなみに、シュウ酸を減らして食べさせる工夫はできます。
キャベツは外側の葉より内側の葉の方がシュウ酸が少ないので、
- できるだけ内側の葉を選ぶ
- 茹でこぼす
などの一工夫でシュウ酸の摂取を減らすことができます。
茹でこぼすとなると、栄養素が豊富に溶けたスープは与えられないということになりますね。
ですが、それでもやはり犬は体も小さいので、シュウ酸は極力避けた方が良いと思います。
欧米では、ミネラル分が多く腎臓へ負担が大きいという理由からキャベツを犬の食べ物にするのは良くないと言われているそうです。
地盤がミネラルを多く含む地域の話のようですが、そのような地盤で育ったキャベツはミネラル分も豊富だからです。
犬にはミネラルウォーターがNGですが、同じ理由でミネラルの多い食べ物の摂取には注意した方がよいということは覚えておきましょう。
キャベツの成分はブロッコリーに似ています。
ブロッコリーは、元々キャベツの一種を改良して作られた野菜です。
なのでやはり共通点も多いようです。
キャベツを使った手作り犬ご飯
犬の手作りご飯にキャベツを使ったレシピは、本でもネットでもたくさん見つかります。
そのまま味付けをすれば、飼い主さんのご飯にもなるようなレシピも多いですよ。
キャベツがおいしくなる春先にぴったりのレシピを見つけましたので、ご紹介してみますね。
<材料>
キャベツ20g
焼鮭(無塩)20g
きんし卵40g
玄米ご飯160g
鶏ミンチ30g1、鶏ミンチを茹でます。あくが出たらとっておきましょう。
網じゃくしなどで、鶏ミンチを取り出しておきましょう。
2、鶏ミンチの茹で汁でキャベツを茹でます。
3、玄米ごはんを二等分して一方に鮭を入れ混ぜます。
4、茹でたキャベツをみじん切りにします。水気を軽くきっておきましょう。
5、お好みの型を用意します。
6、鮭ご飯を下にしき、軽く押します。
7、キャベツのみじん切りをのせ、軽く押します。
8、玄米ご飯をのせて押して下さい。
7、鶏ミンチをのせて押し、型から抜きます。鮭やキャベツなどの混ぜご飯は、お好みで他の食材でお作り頂いても結構です。
8、上にきんし卵や、飾りの茹でたにんじん、ブロッコリーなどをのせて、ひなまつり犬用押し寿司の完成です。
まとめ
キャベツは、満腹感はあるのにカロリーが低く、栄養があり肥満の心配が少ない、使い勝手のよい野菜です。
犬の食べ物には、キャベツの芯を除いて内側の葉を使うのが望ましいです。
日本の地盤で育ったキャベツは、基本的にはミネラルが多すぎるという心配はないです。
ただ、キャベツの注意すべき点だけは押さえておき、上手に食べさせてあげて下さい。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。












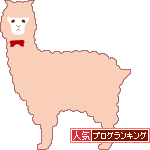
コメント