椎間板ヘルニアは、犬にも多く見られる病気です。
初期から重度まで症状で「グレード」で分類され、進行レベルごとに治療内容も違います。
もちろん早期に治療を開始することが望ましいです。
そこで今回は、犬の椎間板ヘルニアの症状・グレード分類と治療などについて、みなさんと情報共有したいと思います。
椎間板ヘルニアは背骨のクッションが潰れる病気
椎間板とは背骨のクッション部分のこと

犬の背中の骨(脊椎)は、一本の骨ではありません。
背骨は、頸椎7個、胸椎13個、腰椎7個、仙椎3個という椎骨が連なって形成されています。
そこに尻尾の骨(尾椎)が連なって、背骨という身体の軸の骨になっています。
それぞれの椎骨には穴が開いています。
この穴が連なり形成されるトンネルの中を脊髄神経が通っています。
椎骨と椎骨の間には、摩擦や衝撃を吸収するクッションの役割をするゼリー状の組織があります。
これが椎間板です。
椎間板が潰れて神経を刺激する
何らかの原因で、このクッションの役割の椎間板が潰れてしまいます。
そして、脊髄神経側に突出して、神経を圧迫します。
飛び出した椎間板が脊髄神経を圧迫すると、痛みなど、神経由来の症状が起こるようになります。
この病気が椎間板ヘルニアです。
椎間板ヘルニアは、脊椎の「頸椎・胸椎・腰椎」のどの部分でも起こります。
実はヘルニアは他にもある
ここは少し余談になりますので、気楽にお付き合い下さいね。
ヘルニアはラテン語で、直訳すると「脱出」「外に出る」「飛び出す」などの意味があります。
病名に使われるヘルニアの意味は、臓器の一部か全てが、本来あるべき位置から脱出してしまった状態を指しています。
椎間板ヘルニアは、椎間板にこの状態が起こるために「椎間板ヘルニア」と呼ばれるのです。
でもヘルニアと呼ばれる状態は他の臓器にも起こります。
ヘルニアという名前が付く、他の臓器の病気は以下のようなものです。
- 横隔膜が破れて臓器が脱出してしまった:横隔膜ヘルニア
- 臍(へそ)に病変がある:臍ヘルニア(出べそと言われるもの)
- 足の付け根(ソケイ部)に腸が一部脱出した:ソケイヘルニア(脱腸のこと)
- 脳腫瘍などで脳が圧迫されて起こる脳の重篤な病状:脳ヘルニア
好発年齢と犬種がある
犬の椎間板ヘルニアには、2つの型があります。
- ハンセン1型(髄核脱出型)
- ハンセン2型(髄核突出型)
前者は、かかりやすい好発犬種があります。
《ハンセン1型》
軟骨異栄養犬種という分類の犬種があり、これに入る犬種は、若い年から椎間板の変性が起こりやすく、ハンセン1型ヘルニアを発症しやすい好発犬種です。
椎間板の中のゼリー状の組織(髄核)が変質して水分が抜けてしまうため、椎間板は弾力を失い、衝撃を吸収する能力を失います。
そこに日常的な負荷がかかり続けて、椎間板は潰れます。
そして脊髄神経を圧迫し、椎間板ヘルニアの症状が出るのです。
《軟骨異栄養犬種》
ダックスフンド・ウェルシュコーギー・シーズー・ビーグル・ペキニーズ・コッカースパニエルなど
ハンセン1型の好発年齢は3~6歳と若く、初期症状は急性で発症するのが特徴です。
大型犬で、運動量の多いラブラドール・ドーベルマン・ロットワイラーなどの犬種に発症するヘルニアの中にも、この型が見られる場合もあります。
《ハンセン2型》
ハンセン1型に対し、ハンセン2型の方は加齢が原因で発症します。
加齢により椎間板も劣化して変性し、弾力を失って硬くなってきます。
年月をかけて椎間板はじわじわと潰れていき、やがて神経を圧迫して症状が出るようにようになります。
ハンセン2型は成犬~老犬に好発し、経過は慢性的に進行します。
生活習慣も原因のひとつ

犬の椎間板ヘルニアは、発症リスクの高い犬種に加えて、生活習慣も原因のひとつです。
【原因になる習慣】
肥満・跳ねる・体をひねるなどの無理な動き・激しい運動・段差の昇り降り
犬の脊椎は、後ろに反るような動きには大変弱いです。
フリスビーなどでジャンプするような動きも、ヘルニアを起こすきっかけになる動きの1つです。
また、肥満は脊椎に大きな負担をかけます。
特に、遺伝的素因のある犬種にとって、発症リスクを高めるのは肥満であるので、体重コントロールはとても重要です。
椎間板ヘルニアの初期症状

椎間板ヘルニアは、それまで何ともなかった犬に突然、激痛という初期症状が表れます。
しかしよく考えたら、その前から何らかの前兆があったということも少なくないようです。
神経麻痺の症状としては、後ろ足を引きずる症状、ふらつく症状、自分で立ち上がれない症状があります。
重度になると、神経麻痺のせいで痛みなどの一般的な初期症状はむしろ感じなくなってしまいます。
重度の神経麻痺症状には、排尿困難や失禁などがあります。
症状が軽度の時には飼い主さんも気づきにくいようです。
進行して重症になり、神経麻痺の症状が出て初めて病院を受診するケースが多いようです。
そして受診時にはすでに後ろ足が麻痺して動かないようなこともあるそうです。
頸椎の椎間板ヘルニア
頸椎ヘルニアは、小型犬の場合は第3~4頸椎、大型犬は第5~6と第6~7頸椎が好発部位です。
初期症状では、首の痛みがあるので頭を上げられず、うなだれてじっとしているという症状が出現しやすくなります。
振り返るなどの首を動かす動作もできなくなり、強い痛みの症状のために触ると悲鳴のような鳴き声をあげたりします。
頸椎は体の中で大変重要な部分であり、その中を通る神経は脳とダイレクトに繋がっています。
そして首から下の運動や知覚、呼吸、膀胱、直腸などの神経を支配しています。
頸椎ヘルニアで神経圧迫のために症状が重度になった場合、麻痺の範囲は四肢全てです。
麻痺で四肢がふらついて歩行が不安定という症状が初期に見られることもあります。
頸椎は、椎骨7個のうち、第1と第2頸椎(上から数える)は、それぞれ環椎・軸椎という個別の名称で呼ばれます。
この部位は、環椎軸椎不安定症(環軸亜脱臼)という状態を起こしやすい部位で、ヘルニアと似た頸部痛や四肢麻痺などの神経症状が現れます。
胸椎・腰椎椎間板ヘルニア
胸椎・腰椎は、脊椎の中でもっとも動きの多い部位です。
椎間板ヘルニアの8割は、胸・腰椎に発生し、特に、第11胸椎~第2腰椎の間での発生が最も多いとされます。
初期症状は、胸腰部の激しい疼痛で、背中を触ったり抱き上げたりすると悲鳴のような鳴き声をあげ、痛さのあまり威嚇や噛みつきなどの行動が現れることもあります。
症状が進行すれば、下半身や後肢の麻痺が現れ、排尿障害や排便障害という明らかな神経症状も現れます。
神経麻痺のために足の裏をきちんと地面に付くことができず、足をグーの形に折りまげて甲を付けて立つ症状(ナックリング)も特徴的です。
椎間板ヘルニアのグレード分類

犬の椎間板ヘルニアは、重症度のグレード分類があり、グレードの判定が治療法を決める目安になります。
【犬の椎間板ヘルニアのグレード分類】
グレード1:痛みはあるが麻痺はない。普段できていた段差の昇り降りなどができない、抱きかかえると鳴き声をあげるなどの症状がある。
グレード2:痛みに加えて、軽度の麻痺、不全麻痺の症状がある。ふらつき歩行、すり足などが認められる。
グレード3:完全麻痺の症状がある。足の運びができず引きずって歩くなど。
グレード4:麻痺に加えて、排泄障害がある。尿閉や失禁などがある。
グレード5:深部痛覚の消失。痛みを感じることすらなくなる。
特に、ハンセン1型ヘルニアはグレードの急激な進行による症状の急変が多いので、要注意です。
そのグレードは初期症状が出現してから数日で一気に進行することもあります。
椎間板ヘルニアの検査方法と診断
ヘルニアの診断は、症状と神経学的所見、画像検査によって行われます。
椎間板ヘルニアは、一般のレントゲン画像の所見ではわかりません。
レントゲン検査は、ヘルニア以外の骨折や骨の変形がないかを確認する為に行われます。
ヘルニアの診断を確定するには、MRIやCT、脊髄造影レントゲン検査が必要です。
このうち、脊髄造影は古くからある検査ですが、高度な手技が必要な上にリスクの高い検査なので、現在はMRIやCTが現実的でしょう。
ただ、人と違って、犬はMRIにしてもCTにしても全身麻酔が必要です。
やはり検査そのものにリスクを伴うことは免れません。
通常、グレード4以上では手術適応があり、術前に精密な画像検査が必須です。
しかし、初期症状が軽度でグレードが低く、温存治療の可能性が高い場合は、全身麻酔での画像検査をおこなうべきかどうかはケースバイケースになると思われます。
グレード5と脊髄軟化症
椎間板ヘルニアのグレード5は最も重度です。
グレード5では、麻痺症状は進行し、深部痛覚も失っている状態です。
このグレード5の重度の脊髄損傷レベルのヘルニアの約10%に、脊髄軟化症という進行性の病気を発症することがあるとされています。
まれにグレード4でも発症するようです。
脊髄軟化症は、脊髄の強い障害が原因となり、脊髄が溶けて壊死しながら進行していく病気です。
脊髄神経の融解・壊死は全身に広がり、脳の延髄という呼吸などの生命維持に関わる部分にも及びます。
予後は不良で進行も早く、この病気の治療法は確立されていません。
症状は、麻痺などの神経症状だけでなく、食欲がない、元気がないなどの一般症状や、激しい痛みなどもあります。
やがて麻痺の症状は急速に広がり、四肢の麻痺、失禁、呼吸困難などの症状を伴って、数日から1週間程度で亡くなることもある、余命に関わる重大な病気です。
グレード4~グレード5の重度レベルのヘルニアでは、このリスクも考えておく必要があります。
まとめ
犬の脊椎や椎間板の構造は、基本的に人と変わらず、人と同様の椎間板ヘルニアを発症します。
犬の椎間板ヘルニアは、グレードが進行して脊髄損傷になる、重症化しやすい病気の1つです。
症状が重くグレードの高い椎間板ヘルニアは、時に命に関わる危険性もあります。
ヘルニアの好発犬種などは特に、環境の整備や生活習慣に注意し、日常から発症の予防に気を付けてあげて下さい。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。










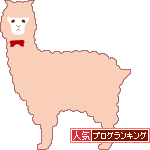
コメント