愛犬がてんかんと診断された時、治るのだろうかということは何よりも心配なのですが、検査や治療にどのくらいの費用がかかるのかという現実的なことも不安な要素ですよね。
そこで今回は、1歳からてんかん治療を続けてきた我が家の愛犬の例を参考にして、検査費用や治療費について情報共有したいと思います。
てんかんと診断されるまで

てんかんは「泡を吹いて痙攣する」という大発作のイメージがあるのではないでしょうか?
でも発作には色々なパターンがあり、発作ということがわかりにくいものもあります。
てんかんの症状や発作の形などは下の記事を参考にして下さいね。
てんかんと似た症状で他の病気の可能性もあります。
そのような病気と区別し、診断を絞り込むためには検査が必要です。
問診
医療機関を受診したらまず問診があります。
これは私達が病院にかかる時と同じです。
《問診の内容》
既往歴・食欲・避妊去勢の有無・ワクチンの時期・発作の経過・発作後の様子など
問診内容は、その動物についての基本的な項目についてです。
かかりつけの病院はすでにカルテがあるので、現在の経過だけで済みます。
発作の様子を撮影した動画などがあれば、それも見せて下さい。
発作の様子を口で説明するのは難しいし、動転していて記憶が曖昧になっているかもしれません。
私の愛犬は発病当時、発作は前兆のような一風変わったものでした。
本格的なけいれん発作ではなく、奇妙な行動があると言った方がいいのかもしれませんが、それをうまく伝えられませんでした。
その時、獣医師から動画を撮るように指導されました。
結局、一度も撮影する機会がなく、典型的な大発作が起こるようになったのですが、もし動画があればわかってもらいやすかったと思います。
神経学的検査
- 犬の姿勢
- 歩行状態
- 麻痺や知覚
- 筋肉の緊張
- 反射
神経学的検査には上記のような基本の項目があります。
それに沿って獣医師が触診をします。
血液検査
感染性の病気など、他に原因になる疾患がないか調べます。
血液は検査項目が多数あり、何を調べるかは獣医師が項目を決めます。
血液検査は情報をたくさん得ることができる検査です。
心電図検査
不整脈など、心疾患がないか確認します。
不整脈には意識を失う病気もあるので、それと区別するためです。
このあたりまでの検査で、脳に問題があるかそれ以外かの目安は大体つくようです。
その病院の方針もあると思いますが、うちの犬はここまでの検査をすべて一通り行いました。
画像検査
脳に問題があると予測される場合、それが何であるかを確認するためにはCTやMRIの画像検査が必要になります。
CTは放射線、MRIは磁気を使用した検査です。
CTやMRI検査を行う時、犬は人間のようにじっとしていることは当然できません。
なので、検査中に動かないように全身麻酔で眠らせる必要があります。
CTの方が検査時間が短いので、人間には負担が少ないと言えますが、犬にとってはどちらも麻酔下の検査なので変わりないでしょう。
画像検査にはそれぞれの利点がありますが、腫瘍や炎症の有無などを精査するなら
、細かい部位がより詳細に見えるMRI検査が選択されると思われます。
最近は大学病院だけでなく、MRI装置やCT装置を持っている民間の動物病院も増えました。
高度医療センターまで行かなくても、民間である程度の診断がつくようになったのは、飼い主にとってもよいことと思います。
ちなみに私の愛犬は、CTもMRIも経験しています。
最初にCT検査を受けましたが、そこでの診断は間違いでした。
セカンドオピニオンを受け、そこでMRI検査を受けました。
人間のてんかんは、脳波の検査が必須になります。
脳波を測定すると、てんかん独特のスパイクという波形が見られるのですが、それが確定診断の所見です。
脳波の測定中は安静が必要であり、しかも長時間かかります。
犬にとってはハードルが高い検査になるので、犬の脳波検査は画像検査ほど高い頻度ではありません。
必要であれば、大学病院などの高度医療施設で麻酔下で実施します。
脳の炎症が疑われる時には、脳脊髄液検査を行うことがあります。
麻酔下で気管内挿管し、脊髄に針を刺して脳脊髄液を採取するという大掛かりな検査で、高度な技術が必要です。
これも高度医療機関などで実施される検査で、一般的に行われる検査ではありません。
検査費用の目安
【MRI検査】
費用は麻酔込みで約5万円~10万円ほどかかります。
費用の設定は、お住まいの地域や病院により差があります。
CT検査の方がいくらか検査費用は安いですが、麻酔の分は上乗せになるので結果的に大差はないと思います。
【血液検査】
どの項目を調べるかによって費用は違い、一般的に項目が増えると費用も上がります。
生化学検査で肝臓や腎臓の機能、炎症反応などの検査項目は必要です。
目安は5000円前後~8000円くらいでしょう。
MRI検査の時に、麻酔と血液検査も込みのセット費用になっている病院もあります。
【神経学的検査】
3000円くらいに設定している病院が多いようです。
【心電図検査】
4000円~8000円くらいです。
【脳脊髄液検査】
血液検査と同様、採取した髄液で検査する項目によって費用が変わります。
麻酔費用は別で、8000円~15000円の範囲で設定されているようですが、それを越える費用がかかる病院もあります。
てんかんの診療費は
- 初診料または再診料
- 検査費用
- 注射などの処置費用
- 薬剤の費用
などを合算したものになります。
犬のてんかん治療の進め方
検査の結果、脳に腫瘍や炎症などの発作の原因が見つかった場合、その脳の疾患の治療が中心になります。
異常所見は見当たらず、てんかん発作の原因が明らかでないものは、特発性(真性)てんかんという診断になります。
この場合は発作のコントロールをする治療を行います。
愛犬は、セカンドオピニオンの病院でのMRI検査で、脳に腫瘍などの原因はないことがわかりました。
それでもてんかん発作を起こしたので、特発性てんかんという診断がつきました。
診断後の検査と定期通院の必要性
治療を開始したら、薬による副作用が出現する可能性も考えないといけません。
それをチェックするために、定期的な検査も必要です。
副作用の検査は血液検査です。
最初は薬の内服開始後2週間~3週間を目安に血液検査をおこないます。
薬の血中濃度や肝障害が出ていないかなどを調べます。
そして薬の投与量が適切か、継続可能かどうかを判断し調整します。
症状と検査のデータを確認しながら、その犬にとって有効かつ最小限度の薬の量を見つけ微調整していきます。
血液検査はその後も定期的に必要です。
獣医師と話し合いながらになりますが、3ヶ月・半年・1年後という間隔を目安にしてチェックしていきます。
通院スケジュールと費用

病状が安定するまでは通院の間隔も短いかもしれません。
安定してくると、1ヶ月に一度くらいで大丈夫です。
何もなければそれ以上の処方も可能と思いますが、これはその病院や獣医師の方針にもよるでしょう。
我が家の場合は、大体1ヶ月に1度の通院をしています。
場合によっては2ヶ月開くこともあります。
動物医療は自由診療なので、人間のように診療報酬の縛りはなく、処方の最大日数もその病院ごとに決められています。
費用も病院によってかなり差があって、薬一つを取っても設定の価格が違っています。
たとえば原価をもとに1錠分の価格を決め、処方した錠数分を計算する方法や、単純に1種類の薬が1日いくらという計算方法をとっている場合もあるようです。
初診料や再診料、検査費用も病院によって違いますので、どの病院を選ぶかによって治療にかかる費用の合算は最終的に大きな差が出るかもしれません。
同じ診療内容で同じ薬をもらっても、費用が全く違うのはこのような理由です。
薬は、犬の体重によっても処方量が変わります。
小型犬と仮定し、再診で30日分の薬をもらったとして、1回の通院にかかる費用は1500円~6000円くらいです。
通院中に行う検査の中で、薬剤血中濃度の検査費用は一般的に高額です。
血中濃度の検査費用は1万円前後かかると考えていた方が無難です。
動物医療は治療も費用もその獣医師の方針、その病院次第。
言い換えれば柔軟性があります。
費用について不安がある場合は、受診を中断したり薬を中断したりするのではなく、ストレートに獣医師に相談してみて下さい。
その上で、どのように治療していくか話し合うといいと思います。![]()
犬のてんかんの治療費用まとめ
てんかんは定期的な通院が必要な病気です。
その都度、処方+検査費用+再診料が発生しますが、高額になる可能性のあるものは検査です。
長期通院になるので、費用も含めた治療内容を獣医師に相談できる関係を築ける獣医師を選ぶとよいですよ。
病院選びはとても重要です。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。







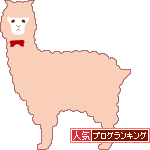
コメント