犬のチェリーアイという病気は、特徴的な外見からそう呼ばれています。
日本語では「第三眼瞼腺突出」というのが正式な病名です。
軽症だと、病気と認識されてないこともありますが、放置していては治らず、他の目の病気に繋がるので、適切な治療が必要です。
根治治療は手術になります。
チェリーアイの手術と費用の目安について調べたことをここで共有したいと思います。
チェリーアイ(第三眼瞼腺突出)は犬のまぶたの病気

チェリーアイとは、犬の目頭の第三眼瞼の裏側にある、第三眼瞼腺が裏返って表に飛び出してしまう病気です。
そう言ってもなかなか想像がつかないですよね。
犬の目頭には、瞬膜とも呼ばれる三番目のまぶた(第三眼瞼というまぶた)があります。
普段は私達と同じように、上下のまぶたを閉じたり開いたりしているのでわからないかもしれません。
第三のまぶたは、涙を浸透させながら眼球を外界の刺激やほこりから保護する役割を持っています。
第三眼瞼の裏側には、涙を生成する第三眼瞼腺があります。
チェリーアイは、本来ならしっかりと軟骨に固定されているこの第三眼瞼腺の固定が悪くなって、目頭から表側に飛び出してしまう病気です。
第三眼瞼腺は、本当ならば目頭の内側にあり、涙を分泌し続けているのですが、それが表に飛び出してしまっているので、十分な涙で眼球を潤すことができなくなります。
そのうえ炎症を起こして腫脹し次第に大きくなって、目やにが多くなったりきちんと目が閉じられないなど、症状が進行していきます。
涙が不足するのでドライアイを併発し、犬は目の痛みを感じ、失明することもあります。
軽症のうちは、炎症を抑えて元の位置へ整復するという保存的治療方法もあります。
でも時間が経過したものやチェリーアイが大きくなったものは、すでにそのような整復もできなくなります。
チェリーアイの根本的治療は手術
チェリーアイを保存的に治療してもよい効果があがらない場合、手術が必要です。
- 飛び出している部分が大きい
- 保存的に押し戻して整復しても何度も再発する
- 長期化・慢性化している
- 他の目の病気を併発している
上記のような場合は、手術の適応になります。
チェリーアイの手術方法は2通りある
手術の方法には、
- 表に出ている第三眼瞼腺を元の位置(目頭の内側)に埋め込む埋没手術
- 突出した部分を切除する切除手術
の2通りがあります。
第三眼瞼腺を固定している軟骨も、表に突出した状態が長期間続くと変形してしまっていることがあります。
その場合は、軟骨も切除し形成する手術も必要になります。
過去の手術方法では、飛び出した第三眼瞼腺を切除する方法が多く選択されました。
しかし、この器官は涙の分泌を担っているので、切除してしまうとその後に深刻なドライアイを併発する問題があります。
そのため近年では、埋没法の手術が多く選択されるようです。
第3眼瞼腺埋没法
埋没法は、近年において主流となっている手術方法です。
埋没手術の方法には、ポケット法とアンカー法という2つの術式があります。
ポケット法は、眼瞼腺の周囲に突出した部分を埋め込むためのポケットを作って、そこに第三眼瞼腺を包みこんで収納し縫合してしまう術式です。
アンカー法は、吸収される糸を使い、突出した第三眼瞼腺を奥の方に埋め込んで糸で引っ掛けて固定し出てこないようにする術式です。
聞いただけでは正直よくわからないですので、ここはざっくりと読み飛ばしてかまいません。
それぞれの病院のやり方、獣医師の方針や経験、手技、手術を受ける犬の状態などで術式は決められますので、実際に手術を受ける場合は獣医師に説明を受けて下さい。
埋没手術は、第三眼瞼腺を切除せず温存することができるので、涙の分泌機能が失われず術後のドライアイの発症リスクを避けることができます。
ただ埋没法手術のデメリットとして、チェリーアイの再発があるようです。
第三眼瞼腺切除手術
第三眼瞼腺を切除してしまう手術方法で、昔はこの手術が主流だったようですが、現在は術後のドライアイのリスクを考慮し、主流ではなくなっています。
第三眼瞼腺は涙の生成の50%近くを担う涙腺である為、切除してしまうと涙の全体量が減少します。
そして術後半年~6年以内にはドライアイによる乾性角結膜炎(KCS)を発症する確率が高くなると言われています。
2種類の瞬膜腺の位置の外科的な整復術が行われたが、ポケット法が最も高い成功率を示した。
長期的なフォローアップでは、外科的に瞬膜腺脱出の整復を行なった犬の方が、治療なし、または瞬膜腺を切除した犬と比べて、KCSの発生率が低かった。
中央値4.8年のフォローアップが33例で可能であり、KCS(STT<10mm/minと定義)は、5.56% (1/18)の瞬膜腺脱出がない犬、37.5% (18/48)の瞬膜腺の既往歴がある犬で発生しています。
フォローアップができた症例では、外科的に瞬膜線の切除を行なった眼では48.1% (13/27)がKCSになったのに対して、タッキング法やポケット法を行った眼ではKCS発生率は14.2% (2/14)でした。
乾性角結膜炎(KCS)は、一度発症すると生涯に渡って治療と管理が必要になり、角膜潰瘍に移行しやすく、潰瘍がひどくなると角膜に穴が開いて失明する可能性もあります。
チェリーアイを治療せず放置している場合も、進行すれば乾性角結膜炎(KCS)になってしまう危険があるのです。
そして切除手術をおこなった場合も、やはり同じように乾性角結膜炎(KCS)になってしまう危険はある、ということになります。
しかし獣医師や病院によっては、現在も切除手術を第一選択にしているところはあるようです。
手術を受ける医療機関を選択する際は、その手術の必要性や術式やリスクなど詳しく説明を受け、セカンドオピニオンで複数の獣医師の意見を聞く、というのは大事なことです。
もちろん状態によっては第三眼瞼腺切除が必要な場合もあります。
「埋没法の手術をおこなってもチェリーアイをたびたび再発する犬」や、「切除法でしか治療できない重度のチェリーアイ」などでは、リスクを承知の上で切除手術を選択せざるを得ないのです。
また、一見チェリーアイにとても良く似た症状で、実は目に発生した腫瘍であるということもまれにあるようで、これはとても重要です。
*参考サイト
「チェリーアイに良く似ている瞬膜(第三眼瞼)の腫瘍(腺癌)」
第三眼瞼腺にできる腫瘍は、ほとんどが悪性の腺腫であり切除手術が必須になります。
チェリーアイと似て異なるこのような病気があることもぜひ意識しておいてください。
手術後の治療
チェリーアイの手術後は、術後感染の予防のため1~2週間にわたり抗生剤の内服や点眼が必要です。
術直後は腫れや充血などが見られ、突出が治っていないように見えていても一時的なものであり、時間の経過と共に腫れが治まり次第に改善していきます。
そして、再発の可能性、チェリーアイが片側の場合はもう片側も発症する可能性、第三眼瞼腺切除手術ではドライアイの発症など、注意すべきことがあります。
薬剤投与は基本的に手術後一定期間で終了ですが、定期的にシルマーティアテストといって、涙液分泌量を測定する検査をしてフォローしていくとよいです。
チェリーアイの手術・治療にかかる費用の目安

チェリーアイが軽度で経過もそれほど長くない場合は、まず保存的治療を試みることが多いので、病院でかかる費用は初診料や検査料、薬の費用の合計になります。
チェリーアイの検査は、主に獣医師による視診や触診で診断がつきます。
しかし腫瘍が疑わしい場合、生検などの検査が必要になるかもしれません。
チェリーアイと診断がついて、消炎剤などの薬で経過を見る場合、犬の体重で薬の量も変わって来ますが、費用は5000円~10,000円くらいになります。
ただ、動物医療は自由診療で、費用の設定もそれぞれの病院で違います。
不安がある場合は大まかに費用の確認をすることをお勧めします。
手術になった場合、全身麻酔で行うので手術前の全身のチェック検査が必要になります。
病院ごとに、手術前検査スケジュールが組まれてあると思いますが、内容としては血液検査、胸部レントゲン、心電図が一般的です。
チェリーアイの手術そのものの費用の相場は、20,000円前後と考えられます。
それに術前検査の費用、麻酔費用、薬剤費用、入院費用などが加算されるのです。
入院日数は、日帰りに対応する病院もあるようですが、1泊入院を基本としているのが一般的です。
それら全て合わせた費用として、合計約30,000円~60,000円が手術にかかる費用の相場のようです。
あくまでも片目の場合であり、両目では約100,000円が標準と考えておいた方がよいでしょう。
また、第三眼瞼腺だけでなく軟骨の変形がある場合は、手術も複雑になるので、手術費用に20,000円程度加算されることになりそうです。
医療保険に入っている場合、チェリーアイが免責事項にあり、保険の対象にならないこともあります。
免責は保険会社によって異なります。
手術の内容、費用と合わせて、保険の免責事項も確認しておいた方が良いです。
まとめ
チェリーアイを発症して経過が長くなると、保存的治療では治癒が望めなくなることが多い病気です。
乾性角結膜炎(KCS)を併発したら失明する危険もあります。
たとえそこまで重症化しなくとも、犬にとっては十分に不愉快な病気です。
もちろん早期に対処したとしても、再発が多いなど、手術も免れないことはあります。
しかし、手術そのものが困難になる前に、気付いたらできるだけ早い時期に治療を行ってください。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。








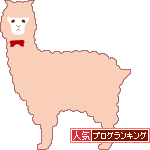
コメント